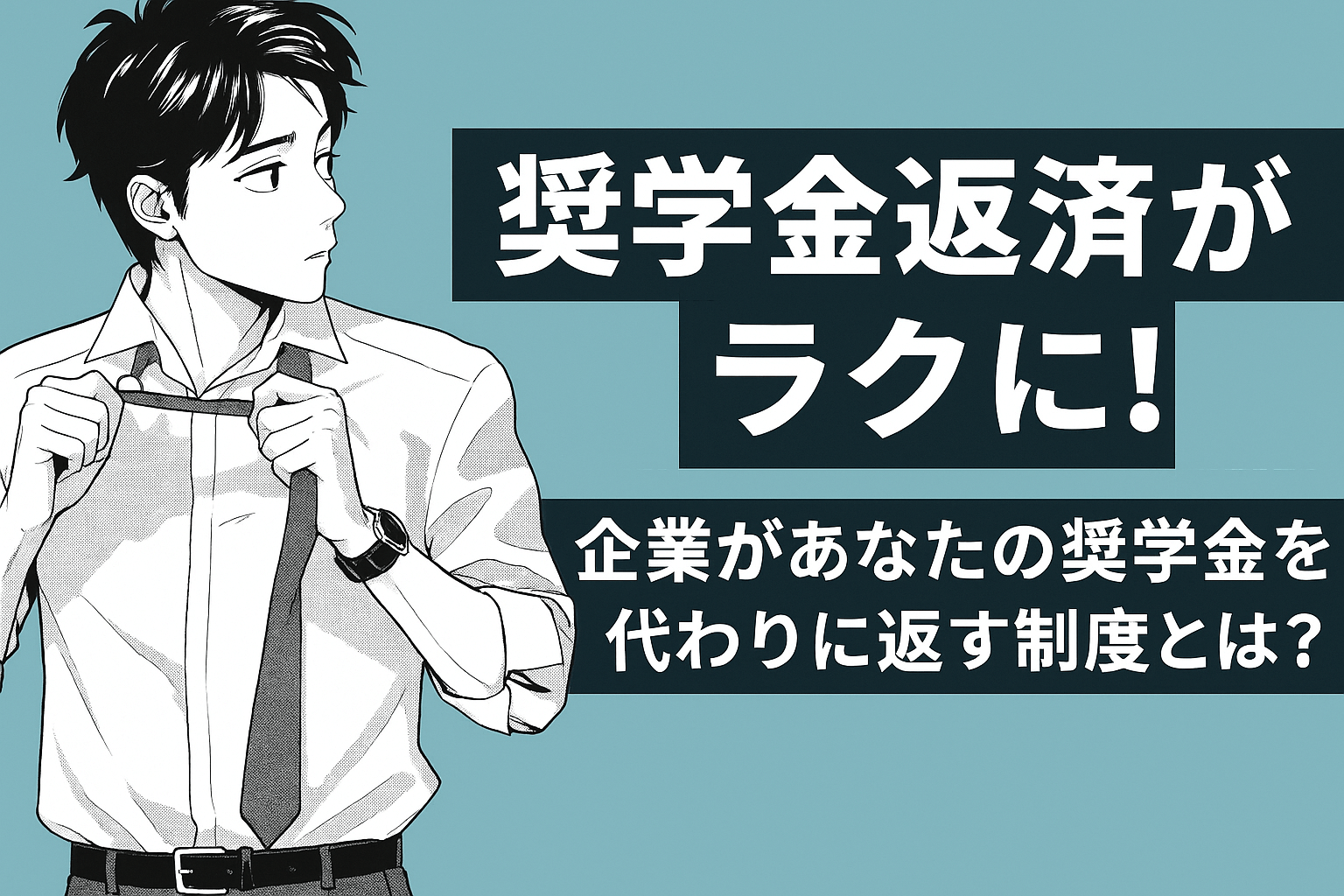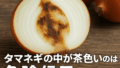はじめに:奨学金が人生を縛る現実
「奨学金は未来への投資」——そう言われて、希望を抱いて大学進学を選んだ人は多いでしょう。
家計の事情で進学を迷ったけれど、「自分の可能性を広げたい」と奨学金を借りる決断をした人も少なくありません。
学生時代は、「卒業後に働いて返せばいい」「何とかなる」と前向きだったはず。
ところが、いざ社会に出てみると、想像以上に返済の負担が重くのしかかってくるのが現実です。

「え、こんなに引かれるの!?」
手取りの給料を見て、ショックを受けた新社会人も…。
奨学金の平均借入額は300万円以上とも言われており、月々の返済額は1万円〜2万円台が一般的。
でも、家賃や生活費、交通費などがかさむ中で、毎月数万円を捻出するのは簡単ではありません。
.png)
「趣味も我慢、旅行も我慢…」

奨学金があるから生活に余裕が持てない、という声もよく聞きます。
その影響で、転職を控えたり、結婚や子育てに踏み切れなかったりする人も増えています。
「もし返済がなければ、もっと自分らしい人生を選べたのに…」という後悔の声も決して珍しくありません。
そんな中、今注目されているのが「奨学金の代理返還制度」という新たな取り組みです。
これは、企業が社員に代わって奨学金を返済してくれる制度で、近年、導入する企業が急増しています。
ただの“優しい制度”ではなく、人材確保や福利厚生の一環として戦略的に導入されているのです。

実はここ1年で導入企業が約1.4倍に増加しているんです!
中には、「この制度があるからこの会社を選んだ」という学生も出てきており、就活市場にも少しずつ影響を与えはじめています。
この制度が広がることで、「奨学金が足かせになっている若者たち」が、もっと自由に、自分らしく未来を選べるようになるかもしれません。
借奨学金の基本:借金としての奨学金制度
進学のための心強いサポートとして知られている奨学金制度。
しかし、その多くは「返さなければならないお金=借金」であることをご存じでしょうか。
日本で利用されている奨学金の多くは、「給付型」ではなく「貸与型」と呼ばれるタイプ。
つまり、卒業後にコツコツ返済していく必要がある、れっきとしたローン(借入)なのです。
よくある勘違いですが、貸与型は“もらえる”奨学金ではありません。
主な奨学金の種類はこの2つ
第一種奨学金(無利子)
・成績などの基準を満たした学生が対象
・返済は必要だが、利子がつかない
第二種奨学金(有利子)
・より多くの学生が対象
・年利上限3%の範囲内で利子がつく(在学中は無利子)
この2種類を合わせて利用している人も多く、卒業時には平均300万円以上の借入があると言われています。
これは大学4年間の学費+生活費をまかなうために必要な金額でもあります。
そしてこの返済は、卒業した翌年の10月頃から始まります。
例えば毎月約16,000円ずつ返済した場合、返済期間は15〜20年以上に及ぶことも。
一見すると「月に1〜2万円くらいなら…」と思うかもしれませんが、社会人になったばかりのタイミングでこの出費はかなりの負担。
特に家賃や交通費、食費などの生活コストを差し引いた手取りの中では、想像以上に圧迫感を感じることが多いのです。

貯金や自己投資が後回しになる人もたくさんいます。
奨学金制度は「誰もが平等に学ぶ機会を得られる仕組み」として確かに価値あるものですが、その反面、長期間にわたって人生設計に影響を与えるのも事実。
こうした現状を踏まえて、今、企業が社員の奨学金を支援する「代理返還制度」に注目が集まっているのです。
新たな選択肢「代理返還制度」とは?
奨学金の返済が重くのしかかる中、今注目されているのが「奨学金の代理返還制度」です。
これは、企業が社員の奨学金を代わりに返済できる仕組みで、2021年から日本学生支援機構(JASSO)が正式に導入しました。

「会社が返してくれるってどういうこと?」

実際に企業がお金を払ってくれる制度なんです!
もともとはアメリカなどで普及していた制度ですが、日本でも若者の経済的負担を軽減し、優秀な人材を確保するための新しい福利厚生として、少しずつ導入が進んでいます。
制度のポイントはこの3つ!
① 社員の手取りが実質アップ
奨学金を企業が代わりに返してくれることで、社員はその分の出費がなくなります。
給与そのものは増えなくても、実際に使えるお金が増える=手取り感がアップするというメリットがあります。

「月1.5万円の返済がゼロになるの、地味にデカい…!」
② 企業側にもメリットがある(課税優遇)
企業が支払う奨学金返済額は、福利厚生費として経費計上が可能。
つまり、企業にとっても節税メリットがあるのです。
国もこの制度を人材支援として後押ししているため、今後さらに広がる可能性も。
③ 採用活動でもアピール材料に
学生や若手社会人にとって、「奨学金を返済してくれる企業」はかなり魅力的な選択肢。
そのため、企業側にとっても採用戦略として有効なポイントになっています。

就活生の最終決断に影響することもあるそうだね。
このように、「代理返還制度」は社員にも企業にもメリットのある“Win-Win”な制度。
導入企業が年々増えている背景には、こうした現実的な利点があるのです。
制度導入企業が急増する理由
「奨学金の代理返還制度」を導入する企業が、いま急激に増えています。
実際、2024年10月時点では2,587社だった導入企業が、わずか8カ月後の2025年6月には3,721社へと急増。
なんと1.4倍以上の伸びを見せており、特に人手不足が深刻な業界(飲食・建設・介護など)での導入が進んでいます。
では、なぜ企業はこの制度を取り入れているのでしょうか?
その背景には、現代の採用・人材定着におけるリアルな課題が見え隠れしています。
■ 理由1:人材確保の“切り札”に
就活生や若手社員にとって、奨学金返済は非常に大きな不安材料。
そんな中、「うちは奨学金を返済支援しますよ」とアピールできる企業は、採用競争で一歩リードすることができます。

「この制度があるだけで、選びたくなる企業になるよね」
実際に、「制度があるからこの企業に入社を決めた」という声も出ており、若い世代に刺さる福利厚生として、強力な魅力となっています。
■ 理由2:早期離職の抑止につながる
新入社員がすぐに辞めてしまう「早期離職」は、多くの企業にとって悩みのタネ。
そんな中、「奨学金を返してくれる会社」に対して、感謝や愛着を持ちやすいという心理効果が注目されています。

「ここまでしてくれる会社、大切にしたいと思うよね」
「せっかく恩を受けた会社だから、もう少し頑張ってみよう」と思う社員が増えれば、離職率の改善にもつながるのです。
■ 理由3:企業にも“おトク”な節税メリット
この制度は、社員だけでなく企業にとっても金銭的なメリットがあります。
というのも、企業が支払った奨学金返還額は、福利厚生費として経費扱いが可能。
つまり、法人税の課税対象から外れる=節税効果があるというわけです。

「社員に喜ばれて、自分たちも節税できるなんて一石二鳥」
コストをかけても得られるリターンが大きいことから、特に中小企業や地域密着型の会社での導入が目立ってきています。
このように、「奨学金代理返還制度」の導入は、採用・定着・節税という3つの課題を同時に解決できる新しい福利厚生として、多くの企業から注目されているのです。
導入企業の具導入企業の具体例
「奨学金の代理返還制度って、実際にどんな企業が導入しているの?」
そう思った方も多いのではないでしょうか。ここでは、すでに制度を導入して成果を上げている具体的な企業の事例をご紹介します。
■ ゆで太郎システム
立ち食いそばチェーンとして全国展開しているゆで太郎システムでは、最大144万円を8年間かけて返済する制度を導入。
現在は社員2名が実際に制度を利用中で、今後入社予定の新入社員にも適用予定だそうです。
飲食業界は人材確保に苦戦している業種のひとつ。だからこそ、若手が安心して働ける環境づくりの一環として、この制度が重宝されているのです。
■ 日本国土開発
総合建設会社の日本国土開発では、最大96万円を8年間で返済する制度を実施。
制度導入から4年間で、なんと52人の社員が制度を利用しています。

「建設業界でも若手の定着に本気なんだな〜」
注目すべきは、「制度利用者の離職率が、制度を使っていない社員よりも明らかに低い」という事実。
企業側も「導入の効果を実感している」と明言しており、人材の安定確保につながる有効な施策として機能していることがわかります。
このように、制度を活用している企業の多くが、「人材定着率が上がった」と実感しています。

「返済の支援=信頼されてるって感じて、辞めたくなくなるのかも」
もちろん返済額や条件は企業によって異なりますが、「社員の人生に本気で寄り添う姿勢」が伝わる点は共通しています。
就活生・若手社員にとってのメリット
「奨学金の代理返還制度」は、単にお金の負担を軽くしてくれる制度ではありません。
若者のキャリアや人生そのものに、大きな影響を与える可能性を秘めています。
ここでは、就活生や若手社会人にとって、どんなメリットがあるのかを具体的に見ていきましょう。
✅ 経済的負担の軽減
何より大きいのは、月々の返済から解放されること。
たとえば月に15,000円返済していたとしたら、それがなくなるだけで家計のゆとりがかなり変わってきます。

「その分、貯金や趣味に使える!これは嬉しい〜」
手取りが少ない新卒時代には、この差が生活の安心感や充実度に直結するんです。
✅ キャリア形成への安心感
返済に追われていると、「給料のいい仕事じゃないとダメ」「転職すると返済が不安」といった理由で、キャリア選択を狭めてしまうこともあります。
しかしこの制度があると、自分に合った仕事をじっくり選ぶことができるようになります。
資格取得やスキルアップなどの自己投資にも時間とお金をかけられるので、長期的な視点でキャリアを考えることが可能に。

「焦らずに成長できる環境って、実はすごく貴重なんだよね」
✅ 精神的ストレスの軽減
「毎月の返済日が近づくたびにソワソワ…」そんな心の負担からも解放されます。
借金があるという事実だけでも、無意識のうちにストレスを感じるもの。
奨学金の返済がなくなることで、心にゆとりが生まれ、前向きな気持ちで日々を過ごせるようになる人も多いんです。

「気持ちに余裕があると、仕事にもプライベートにも良い影響が出るよね」
このように、「代理返還制度」は単なる金銭的サポートではなく、“人生の選択肢を広げる制度”として、大きな価値を持っています。
「代理返還制度」利用で人生はどう変わる?
奨学金の返済があることで、知らず知らずのうちに人生の選択肢が狭まっている――そんな実感を抱いている人は少なくありません。
でも、企業が返済をサポートしてくれる「代理返還制度」を活用すれば、前向きな変化が生まれるのかもしれません。
✅ 就職時の企業選びが“将来基準”に変わる
奨学金返済の不安があると、どうしても「初任給の高さ」や「手当の多さ」で企業を選びがち。
でもこの制度があると、本当にやりたい仕事や、成長できそうな会社に目を向けられるようになります。
💬 「給料より制度の中身で会社を選ぶようになったかも」
つまり、短期的な安心感よりも長期的なキャリア形成を重視できるようになるのです。
✅ 結婚・出産など将来のライフイベントにも前向きに
奨学金の返済が続くと、「お金のことで家庭を持つのは不安…」と考える人も多いですが、代理返還制度を活用すればその不安がかなり和らぎます。
実際に、制度を利用して結婚や出産を前向きに考えられるようになったという声も。
人生の大きな決断にも、自信を持って一歩を踏み出せるようになるのです。
✅ ダブルワークや過重労働からの解放
「返済のために深夜バイト」「ブラック企業でも我慢」…そんな生活をしている人も少なくありません。
でも、企業が奨学金を返してくれるなら、無理な働き方をしなくても大丈夫。
ワークライフバランスの取れた職場で、自分らしい働き方を選べるようになります。
体力的にも精神的にも無理をせず、“ふつうの生活”を安心して送れるようになるのは、とても大きなメリットです。
このように、「奨学金代理返還制度」はお金の問題を解決するだけでなく、人生全体の選択肢を広げてくれる制度です。
若者たちの声:奨学金返済の苦しみ
奨学金を借りて大学に通う若者は、今や当たり前の時代。
しかし、社会人になった途端に始まる長期にわたる返済生活は、想像以上に重く、苦しいものです。
実際にSNSやインタビューなどでは、以下のようなリアルな声が多く聞かれています。
■ 「副業しても生活はギリギリ」
正社員として働いていても、毎月の返済に追われて自由に使えるお金がないという若者は少なくありません。
そのため、夜や休日に副業をしてなんとか生活費を捻出しているという人も…。
このような生活が続けば、心も体も疲弊してしまうのは当然です。
■ 「ブラック企業でも辞められない」
もっと条件の良い職場に転職したくても、奨学金の返済がネックとなって辞められないというケースも多いです。
特に「給与が途切れたら即アウト」という状態では、選択の自由が大きく制限されてしまいます。
💬 「辞めたいけど、奨学金の返済があるからガマンしてる」
「やりたい仕事より、返済できる仕事を優先せざるを得ない」――これが現実です。
■ 「死ねばチャラ」…追い詰められる若者たち
中には、あまりにも返済が重くのしかかり、「死ねばチャラになる」と口にする若者までいます。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金は、基本的に本人が亡くなった場合、返済義務は消滅するため、極限状態に陥る人も存在しているのです。
💬 「生きてるだけで負担。なんで学びたいって思っただけで、こんなに苦しまないといけないの?」
こうした声は、見過ごすことのできない社会の叫びでもあります。
■ 若者自身が立ち上がり始めた
一方で、声をあげる若者も増えています。たとえばZ世代の間では、「奨学金帳消しプロジェクト」のようなムーブメントが生まれており、社会に対する制度改革の要望も高まりつつあります。
こうしたリアルな声を受け、「返すのが当たり前」という前提を見直す時期に来ているのでは?という議論も活発になっています。
社会的な背景と課題
そもそも、なぜここまで奨学金の返済が若者の負担になっているのでしょうか?
それには、日本社会特有の構造的な問題が深く関わっています。
■ 「奨学金」という名の“借金”
日本の奨学金制度は、実質的には「学生ローン」と呼べるような仕組みになっており、貸与型が中心です。
つまり、「学びたい」という想いを叶えるために、多くの学生が数百万円単位の借金を抱えることになるのです。

「学生のうちから借金を背負うって、やっぱり重すぎるよね…」
特に欧米のように給付型奨学金が主流の国と比べると、日本はまだまだ支援が十分とは言えない状況です。
■ 低賃金と不安定な労働市場
奨学金制度の重さをさらに苦しくしているのが、低賃金や非正規雇用の増加といった日本の労働環境の現実。
新卒で正社員になっても、手取りは月15万円前後というケースもあり、奨学金の返済が家計を圧迫してしまいます。
このような労働環境の中では、「借りたら返せる」という前提そのものが成り立たないとも言えるでしょう。
■ 救済制度の少なさと自己責任論
返済が苦しい人のための救済制度はあるものの、申請手続きが複雑だったり、条件が厳しかったりして利用が進まないという課題もあります。
また、「借りたのは自分なんだから、返すのが当然」という自己責任論が根強いのも、支援が広がりにくい一因です。
■ 代理返還制度が切り開く“企業からの支援”という可能性
そんな中で注目されているのが、企業が奨学金返済を支援する「代理返還制度」です。
これは、行政だけに頼らず、民間企業ができる範囲で若者を支える動きとして、大きな可能性を秘めています。
まだ導入企業は全体の一部に過ぎませんが、今後こうした制度が広がれば、若者を取り巻く環境も少しずつ変わっていくかもしれません。
まとめ:制度の拡大と今後への期待
「奨学金=未来への投資」と言われながらも、現実には何百万円もの借金として若者の人生にのしかかっている奨学金制度。
そんな中で登場した「代理返還制度」は、まさにその構造に風穴を開ける新しい選択肢です。
この制度の魅力は、単に「返済の肩代わり」だけではありません。
企業にとっても人材確保や離職防止、税制上の優遇といった多くのメリットがあり、導入企業が急増しているのも納得です。
さらに、この制度が社会にもたらす影響はとても大きく、若者のキャリア形成・結婚・出産・住宅取得など、人生のさまざまな場面に前向きな変化を与える可能性を秘めています。
教育の機会均等や、経済格差の連鎖を断ち切るための手段としても、今後ますます重要な制度となるでしょう。

「学びたい」という気持ちに、もっと優しい社会であってほしいです。
今後は、企業の取り組みに加えて、国や自治体による制度の拡充や、さらなる認知の広がりにも期待したいところです。
学生、就活生、若手社会人、そして企業がそれぞれにメリットを享受できるこの制度が、より多くの人に届くことを願っています。
最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。
この記事が、奨学金返済に悩む誰かの希望につながればうれしいです。
参考サイト