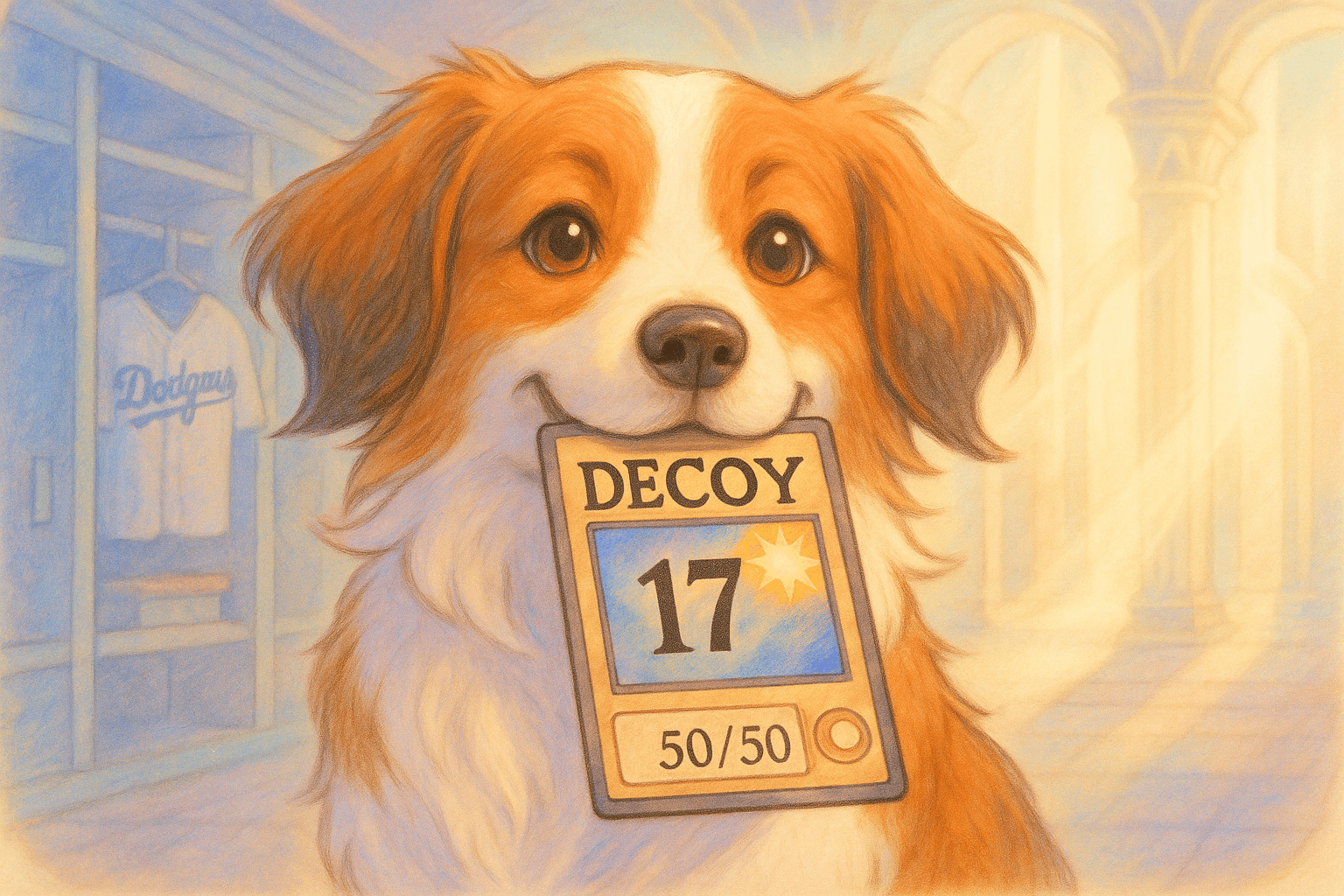ソフトバンクが2026年から試験的にスタートさせる「空飛ぶ基地局(HAPS)」サービス。
“空に浮かぶ通信基地”というまるでSFのような構想が、いま現実のものになろうとしています。
最近ではテレビやネットニュース、SNSなどでも少しずつ話題に上るようになり、
「HAPSってなに?」「なんで空に基地局を飛ばすの?」「どんなことに使えるの?」
といった疑問の声が多く聞かれるようになってきました。
この空飛ぶ基地局には、災害時の通信確保、過疎地域のネット整備、さらには次世代インフラへの期待など、たくさんの“未来”が詰まっています。
特に日本のように地震や台風など自然災害が多い国では、空から通信を支えるという仕組みは非常に現実的で、注目されているのも納得です。
本記事では、ソフトバンクの公式発表をもとに、
- HAPSとは何か?
- ソフトバンクがこの技術に注力する理由
- 技術の仕組みや特長
- 今後のスケジュールや実証試験の動き
- 想定される活用シーン
などをわかりやすくご紹介していきます。
“通信の常識”を変えるかもしれない最新プロジェクト、その実像をぜひ最後までチェックしてみてください。
✅ HAPS(ハップス)とは? 空飛ぶ基地局の仕組み
HAPS(High Altitude Platform Station/成層圏通信プラットフォーム)とは、地上から約20km上空の“成層圏”に飛行機型の無人機を長時間滞空させ、空から電波を届けるという新しい通信インフラのことです。
「空飛ぶ基地局」とも呼ばれ、ソフトバンクをはじめとした通信企業が次世代インフラとして注目しています。
従来の基地局は地上に設置されており、山間部や離島など、どうしても電波が届きにくい“通信の空白地帯”がありました。
ですがHAPSなら、高い場所から広いエリアを一気にカバーできるため、そうした場所にも安定した通信を届けることができるのです。
HAPSの特徴をもう少し詳しく見てみましょう。
🔹 高度約20kmの成層圏を飛行
HAPSが飛ぶのは、飛行機よりも高く、人工衛星よりも低い“成層圏”というエリア。
ここは気流が比較的安定しており、天気や雲の影響を受けにくいため、長時間の安定した飛行と通信が可能です。
🔹 広範囲を一機でカバー
成層圏から地上を見下ろす形になるため、1機のHAPSで地上の数百kmもの広さをカバーすることができます。
これにより、基地局の設置が難しい山奥や離島などにも通信エリアを拡大できるのが大きな強みです。
🔹 低遅延でリアルタイム通信に強い
「空から通信」と聞くと、衛星通信を思い浮かべるかもしれませんが、HAPSは衛星よりもずっと地表に近いため、電波の伝送にかかる時間(遅延)がかなり短く済みます。
そのため、スマートフォンはもちろん、自動運転車やドローン、工場のIoTシステムなど、リアルタイム性が求められる通信にもぴったりです。
未来の通信インフラとして、HAPSにはとても大きな可能性があります。
では、なぜソフトバンクがこのHAPSに本気で取り組んでいるのでしょうか?
✅ ソフトバンクが発表した「空飛ぶ基地局」計画概要
2025年6月26日、ソフトバンクがついに正式発表しました。
それは――**「空を使った新しい通信インフラを、2026年から日本国内で本格的に始める」**という内容です。
これまで実証実験を重ねてきた「HAPS(空飛ぶ基地局)」ですが、いよいよ実際のサービスとして動き出す段階に入ったということで、大きな話題となりました。
今回の発表で明らかになった主なポイントは以下の通りです。
🔸 2026年に国内でプレ商用サービスをスタート予定
まずはごく限られた地域・用途に限定した**“お試し運用”のフェーズ**から始まります。
この段階では利用者数も少なく設定され、実際の運用環境で技術やシステムの安定性を確認しながら進めていくとのこと。
🔸 最初の用途は「災害時の通信確保」を想定
特に注目されたのが、大規模災害への備えとしての活用です。
たとえば、地震や台風などで地上の基地局が壊れてしまった場合、被災地の上空にHAPSを飛ばし、
臨時の通信手段として活用するというシナリオが想定されています。
日本のように自然災害が多い国では、通信インフラの強靭化は非常に重要なテーマ。
HAPSが空から“つながる手段”を確保してくれるなら、大きな安心材料になりそうですね。
🔸 本格的な商用化は2027年以降を予定
2026年のプレサービスで得られた運用データやフィードバックをもとに、HAPSの信頼性やコスト、対応エリアなどをさらに改善し、2027年以降には一般向けサービスとして展開していく計画です。
まだ始まったばかりのHAPSプロジェクトですが、ソフトバンクの本気度はかなり高そうです。
✅ 米Sceye社製の飛行船型HAPSを導入
今回、ソフトバンクがHAPS実現に向けてパートナーとして選んだのが、アメリカ・ニューメキシコ州に拠点を置くSceye(スカイ)社。
同社は、“飛行船型”のHAPS(成層圏通信プラットフォーム)に特化した開発を進めている企業として、海外でも注目を集めています。
ソフトバンクはこのSceye社に対し、約22億円の出資を行い、同社が手がける最新型の飛行船型HAPSの導入を決定しました。
🌤️ その飛行船って、どんなもの?
公式発表では、導入予定の飛行船型HAPSについて、次のようなスペックが公開されています。
- 全長:約65メートル
→ ビル20階相当の長さ!想像以上に巨大です。 - ヘリウムガスで浮かぶ構造
→ 気球のように空へ浮かび、成層圏で静かに滞空。プロペラで姿勢制御も可能です。 - 太陽光パネル+バッテリー駆動
→ 日中に太陽光で発電し、そのエネルギーを使って夜間も飛行を継続。持続可能な仕組みが魅力です。 - 通信設備を搭載
→ 携帯電話の基地局用アンテナなどを積み込んで、成層圏から地上の端末に電波を届けます。
🌱 なぜ「飛行船型」なの?
HAPSには大きく分けて「飛行機型(HTA型)」と「飛行船型(LTA型)」がありますが、今回ソフトバンクが選んだのは、**LTA型(Lighter Than Air:空気より軽い)**です。
飛行船型の大きなメリットは、消費エネルギーが少なく、長時間空中にとどまることができる点にあります。
飛行機型に比べて構造がシンプルで燃料効率もよく、メンテナンス性にも優れているとされており、長期運用に適しているのです。
これだけ巨大でエコな飛行船が、空からスマホに電波を送ってくれる――。
まるで映画のような話が、いま現実になろうとしています。
✅ 2026年のプレ商用サービスとは?
ソフトバンクが2026年に始めると発表した「プレ商用サービス」。
ちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは本格的な商用運用に向けた“お試し期間”のようなフェーズです。
いきなり全国で使えるようになるわけではなく、あくまで限られた条件の中で、実際にどのように運用できるのかを検証していくためのステップとなります。
🛫 プレサービスの具体的な内容は?
今回の計画では、まず国内に1機の飛行船型HAPSを導入し、実際に空へ飛ばすことになります。
その機体は先に紹介した米Sceye社製のもの。約65メートルの巨大な飛行船が、成層圏の高さに浮かびながら通信を届けるわけです。
- 運用期間はおよそ10日間程度を想定
→ 成層圏で安定して飛び続けられるか、そしてその間の通信品質はどうか?という点を重点的にチェックします。 - 対象エリアや利用者は限定的
→ たとえば特定の自治体や、防災関連の機関など。試験的な位置づけなので、誰でも使えるわけではありません。 - 収集した通信データで品質を評価
→ 実際にどのくらい安定して通信できるのか、気象や高度の変化にどんな影響を受けるのか…といったデータを細かく収集し、将来の本格サービスに活かしていきます。
👷♂️ 初年度は災害対策に重点を置いた運用に
2026年の段階では、**一般のスマホユーザーが自由に使えるサービスではなく、主に関係機関向けの“試験利用”**になります。
特に力を入れているのが、災害対策。
地震や水害など、地上の通信網が壊れてしまうような場面で、HAPSが“空からの通信手段”としてどれだけ機能するのかを検証するのが主な目的です。
「空からつながる」という未来が、少しずつ現実味を帯びてきました。
✅ 2027年以降の本格運用を目指す
2026年のプレ商用サービスを経て、ソフトバンクは2027年以降にHAPSを本格的に運用していくことを目指していると発表しています。
テスト段階で得られる実証データや運用経験をもとに、より実用性の高いサービスへと進化させていく計画です。
その中で掲げられているのが、以下のような**“空からつながる社会”を支える活用ビジョン**です。
📡 災害時に即応できる“空飛ぶ通信インフラ”へ
日本は地震や台風などの自然災害が多い国。
そうしたとき、地上にある基地局が壊れてしまうと、携帯電話やインターネットが使えなくなってしまう恐れがあります。
そこで期待されているのがHAPS。
被災地の上空にHAPSを素早く派遣すれば、一時的な“空の基地局”として通信をカバーすることができるのです。
これにより、救助活動や避難所の連絡、家族との安否確認など、災害時に命を守る通信手段としての活用が期待されています。
⛰️ 山間部や離島でも“つながる”を当たり前に
HAPSは、災害時だけでなく、普段から通信が届きにくいエリアの常設インフラとしての役割も期待されています。
たとえば、山奥の集落や離島など、地上に新たな基地局を設置するには多大なコストと時間がかかります。
しかしHAPSを使えば、そうした場所でも地上設備に頼らずに安定したモバイル通信を提供できるようになります。
「基地局を空に浮かべる」という発想が、これまで通信が届かなかった場所にも“つながる”安心を届けてくれるんですね。
🤝 日本全体のインフラ強化へ広がる期待
このHAPS技術、実はソフトバンクだけが注目しているわけではありません。
NTTドコモなど他の通信大手も、HAPSを含む次世代通信インフラの研究開発を進めているのです。
つまり今後は、日本の通信業界全体で**“空から支えるインフラ”を共に進化させていく動き**が加速していく可能性があります。
次世代のインフラとして、災害にも強く、どこにいても“つながる”社会を支えるHAPS。
その実現に向けた取り組みは、すでに本格的に動き出しています。。
✅ 今後のスケジュール|HAPSはいつ実用化される?
では、ソフトバンクの「空飛ぶ基地局(HAPS)」は、これからどのようなステップを経て私たちの暮らしに登場するのでしょうか?
公式発表をもとに、現在わかっているロードマップをわかりやすくまとめてみました。
📅 2025年:準備フェーズに突入
すでにソフトバンクは、HAPSの国内飛行に関する許可を取得済み。
これにより、日本の空で本格的な運用を進めるための法的なハードルはクリアされています。
今は、機体の導入やシステム開発、関係機関との連携など、サービス提供に向けた準備が進行中。
HAPSが実際に空を飛ぶ日が、いよいよ現実味を帯びてきました。
📅 2026年:プレ商用サービス開始
いよいよHAPSが空に飛び立つタイミングがこの年。
まずは限られたエリア・利用者向けに“お試し運用”がスタートします。
この段階では、本格サービスに向けた技術検証が主な目的。
飛行船型HAPSの性能、通信の安定性、運用コストなどを細かくチェックしながら、将来の展開に必要なリアルなデータを収集していきます。
なお、このプレサービスは、一般ユーザーが使える形ではなく、災害対策や官公庁向けの試験利用がメインになる予定です。
📅 2027年以降:一般向けに本格サービス開始へ
プレ商用フェーズで得られた知見をもとに、いよいよ一般向けのHAPSサービスがスタートします
このタイミングでは、
- 災害発生時の通信手段として即時対応
- 山間部・離島など、地上インフラの整備が難しい地域への通信提供
といった形での活用が本格的に進められていく見通しです。
将来的には、HAPSが全国の通信インフラの一部として当たり前に使われるようになる日も、そう遠くないのかもしれません。
✅ まとめ|“空からつながる未来”はもう始まっている
ソフトバンクが2026年に開始を予定している「空飛ぶ基地局(HAPS)」サービス。
これは単なる新しい通信技術ではなく、日本全体のインフラのあり方を変えるかもしれない、大きな一歩です。
HAPSは、次のような社会的な意義を持っています。
✅ 成層圏から広範囲をカバー
→ 地上からでは届きにくかった山間部や離島にも、空から安定した通信を届けることが可能に。
✅ 災害時の緊急通信インフラとして活躍
→ 地上の基地局が被災しても、HAPSが代替通信手段として迅速に機能。命を守るインフラになる可能性も。
✅ 通信格差の解消に貢献
→ 都市部と地方との“つながりやすさ”の差を埋め、誰もが当たり前にネットにつながる社会へ。
もちろん、現時点ではまだ技術検証の段階であり、
- 成層圏での長時間滞空の安定性
- 通信品質の確保
- 大規模運用におけるコストやメンテナンス体制
など、乗り越えるべき課題も多く残されています。
しかし、すでに飛行許可を取得し、2026年のプレサービスが決まっていることからも、HAPSが“実現目前の未来技術”であることは間違いありません。
これからどこまで実用化が進み、どんな形で私たちの暮らしに影響を与えてくれるのか――
通信の未来を考えるうえで、今後もHAPSの動向から目が離せませんね。
.png)