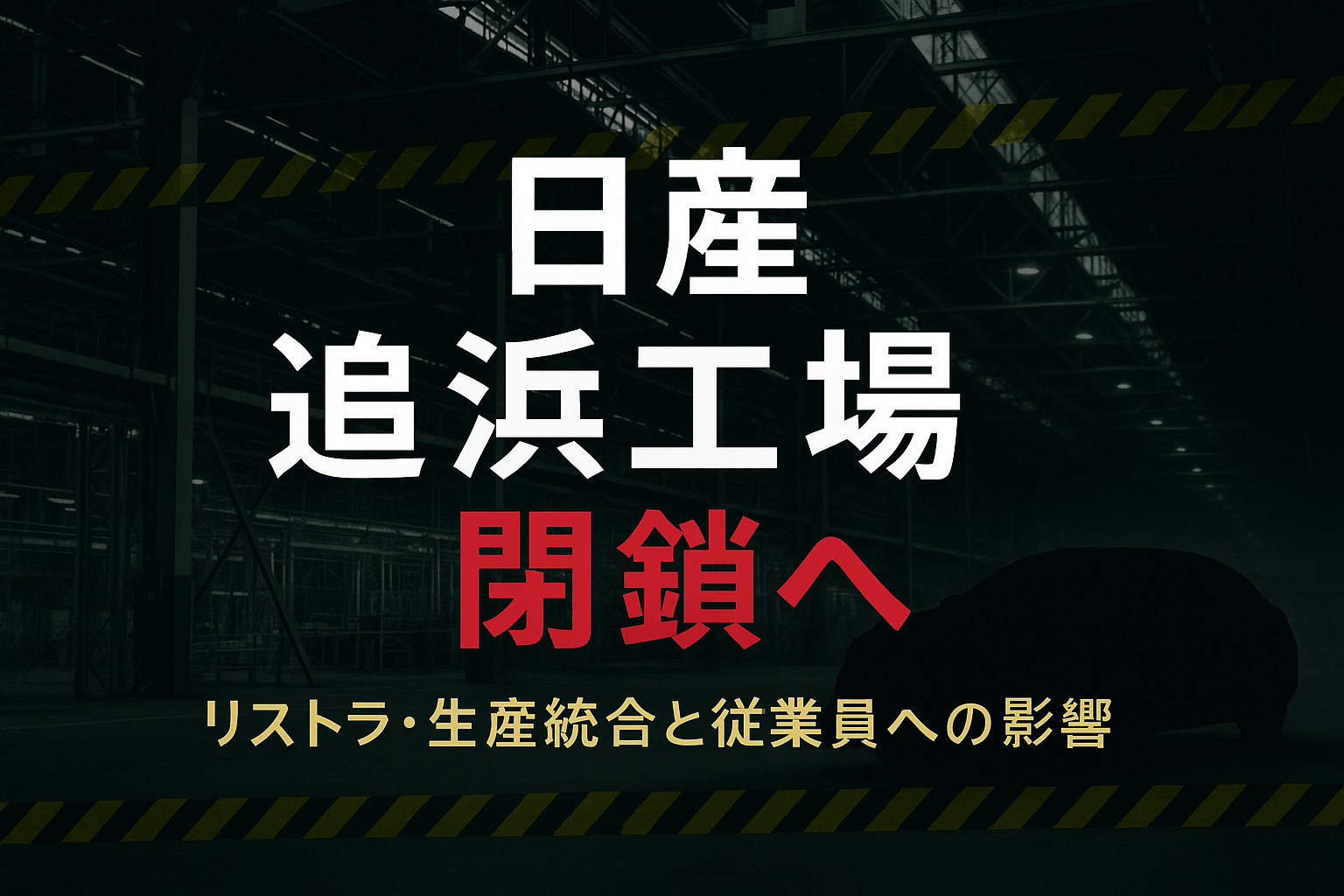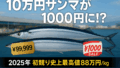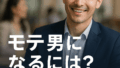2025年5月、日産自動車が経営再建に向けた新たな一手を発表しました。
その名も「Re:Nissan」計画。
長年のブランドを背負ってきた日産が、国内外での大規模な構造改革に踏み出す姿勢を示しています。
中でも大きな衝撃を呼んでいるのが、神奈川県横須賀市にある「追浜(おっぱま)工場」の閉鎖方針です。

追浜工場ってどんなところ?

1961年から稼働を開始。スカイラインなどの生産でも知られ、「日産の魂」とも呼ばれた工場なんです!
追浜工場は、まさに日本のモータリゼーションの象徴的存在。
その歴史は60年以上にも及び、自動車産業の発展を支えた場所でもありました。
しかし、今回の決定は、世界的な販売不振や過剰な生産設備、そして経営戦略の迷走といった複合的な要因によって導かれたものです。
追浜での生産は段階的に縮小され、今後は九州工場へと集約されることになります。
さらに、かつて日産が模索していた台湾の大手企業・鴻海(ホンハイ)とのEV事業の協業についても、条件面で合意に至らず立ち消えになったと報じられています。
こうした戦略の混乱も経営難に拍車をかけているのが現状です。
日産×鴻海(ホンハイ)のEV協業検討が意味するものとは?追浜工場での生産案、雇用維持への期待と課題を徹底解説

あのホンハイって、iPhone作ってる会社のこと?

そうです!EVでも業界に参入していて、各国の自動車メーカーと提携を進めているみたいです。
今回の記事では、この追浜工場の閉鎖をめぐる動きに焦点を当てながら、以下のような疑問に対して丁寧に解説していきます。
今後の日産はどこへ向かうのか?
なぜ、日産は今このタイミングでリストラに動いたのか?
追浜工場の閉鎖は、地域社会や従業員にどんな影響を与えるのか?
経営陣の判断は正しかったのか、それとも…?
今回の動きが自動車業界全体にとってどんな意味を持つのか、そして今後の日産に求められるものは何かについても、あわせて解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
【日産自動車の追浜工場閉鎖が正式発表
【2027年度末での生産終了を発表
2025年5月、日産は追浜工場の車両生産を2027年度末で終了すると公式に発表しました。
同時に、同じ神奈川県内の日産自動車の子会社である日産車体湘南工場も、2026年度に車の生産を終えることが発表されました。
追浜工場は小型車「ノート」などを製造し、年24万台分の生産能力を持つ日産の中核拠点。
1961年の操業開始以来、60年以上にわたり地域と共に歩んできました。

「追浜工場は、世界でいち早くEVの量産を始めた日産の象徴的な工場」
しかし、2024年時点での稼働率は約4割に低下。
一般的に自動車工場の損益分岐点は7〜8割とされ、持続的な操業が難しくなっていたのです。
.png)
「どうしてそこまで稼働率が下がったの?」
✅ 需要の落ち込みや世界市場の戦略変更、車種モデルの切り替えなどが重なり、特定の工場だけで安定して生産を続けるのが難しくなった背景があります。
追浜工場閉鎖の背景にある「Re:Nissan計画」
世界的な販売不振と巨額赤字
日産自動車は2025年3月期決算で最終利益が6708億円の赤字という衝撃的な数字を公表しました。
世界的な販売不振が主因であり、南アフリカ、インド、アルゼンチンなどでの生産も終了。
メキシコの2工場も削減予定です。
「国内外で17ある完成車工場を10にまで減らす」
というのが「Re:Nissan計画」の大きな柱。
国内でも追浜を閉鎖し、栃木工場と九州の2拠点に集約します。

「世界で約2万人削減する計画も発表されています。」
✅ これは全従業員の約15%に相当し、国内外問わず広範囲に及ぶ大リストラ策です。
経営陣が問われる責任
そもそも、なぜここまで追い込まれたのでしょうか。
その要因の一つは、経営陣の打ち出したグローバル戦略の失敗にあります。
- EV戦略の停滞
- 収益性の低い地域への過剰投資
- 日産・ルノー・三菱連合の軋轢
など、経営トップの決断ミスが積み重なり、再建には痛みを伴う構造改革が不可避となったのです。

「ちなみに追浜工場は、日産初のEV『リーフ』を量産した場所です。」
✅ EVシフトを象徴する工場だっただけに、閉鎖のインパクトは大きいです。
九州工場への生産統合と今後の計画
追浜工場で行われていた車両の生産は、今後福岡県にある日産九州工場へと順次移管・統合される予定です。
日産九州工場は、最新の生産設備や物流体制が整っており、生産効率やコスト面でも有利な拠点として知られています。
国内外に向けた多品種少量生産にも柔軟に対応できることから、日産としては「規模の経済」を活かして、グローバルな供給体制を再構築していく狙いがあります。
ただし、生産拠点の再編にはメリットばかりではありません。
従業員の異動や再配置、地域経済への影響など、現場レベルでは多くの課題が残されています。
なかでも注目されているのが、追浜工場で働く約2400人の今後の雇用問題です。
従業員約2400人の雇用はどうなる?
追浜工場では現在、およそ2400人の従業員が車両生産に携わっています。
工場の閉鎖が正式に決定しても、2027年度末の生産終了までは今の体制で稼働が続く予定です。
その後の雇用については、日産と労働組合との間で現在も協議が進められています。
日産側は、
「雇用を最優先に、あらゆる可能性を検討する」
と説明しており、希望退職を募るだけでなく、他工場への配置転換やグループ内での再雇用など、複数の選択肢が検討されているようです。
ただし、具体的な内容や個別対応についてはまだ明らかにされていません。
.png)
「全員が九州に転勤するの?」

いいえ、そう決まったわけではありません。
早期退職や他部署への異動など、複数の選択肢が今後提示される見込みです。
今回の閉鎖は、企業としての効率化や生き残り策の一環ではありますが、そこで働く人々にとっては生活に直結する大きな変化。
だからこそ、日産には従業員一人ひとりの立場に寄り添った、誠実な対応が求められています。
地域経済への影響は大きい
追浜工場の閉鎖が、単に一企業の工場再編にとどまらない問題であることは、多くの人が感じ始めています。
そもそも神奈川県は日産の本社がある“地元”。
追浜工場も1961年の稼働開始以来、地元に根づいた存在として、地域経済を長年にわたって支えてきました。
とくに近隣地域には、部品メーカーや物流、メンテナンスなど数多くの関連企業が集まっており、経済的なつながりが非常に強いのです。
こうした背景から、今回の工場閉鎖は地域の中小企業の受注減、さらには雇用喪失による個人消費の落ち込みなど、複合的な経済ダメージにつながると見られています。
.png)
「閉鎖って、日産だけの問題じゃないの?」

実は取引先企業や地元の雇用、自治体の財政にも影響が出るんです。
とくに心配されているのが、人口流出のリスクです。
働き口が減ることで若年層が地元を離れ、地域の活力が失われる――そんな負の連鎖も懸念されています。
また、自治体にとっても日産のような大企業の存在は、固定資産税や法人市民税といった財源の柱。
追浜工場の閉鎖は、こうした税収減にもつながりかねません。

「地元にとって“日産”はどれくらい大きな存在だったの?」

横須賀市の雇用や経済、交通網にも深く関わってきた、まさに“地域の要”といえる存在です。
企業の合理化が求められる一方で、地域への配慮をどうバランスよく進めていくかが、これからの課題となりそうです。
「工場閉鎖は仕方ない」だけで終わらせていいのか?
今回の追浜工場の閉鎖について、日産は「持続可能な経営のために痛みを伴う決断が必要だった」と説明しています。
確かに、工場の稼働率が4割程度にまで落ち込んでいたことを踏まえると、経営的な判断として理解できる面もあるでしょう。
しかし、ここで大切なのは、「なぜこうなってしまったのか」という根本原因の検証と、「その責任はどこにあるのか」という視点です。

「やっぱり、こうなる前に手は打てなかったのかな…」

“仕方ない”で終わらせる前に、原因や責任をしっかり振り返る必要があると感じます。
経営の効率化や再建は確かに重要です。
ただ、その過程で一番大きな痛みを負うのは、現場で働いてきた従業員や地元の人たちです。
だからこそ、「工場閉鎖は会社の都合で決まったこと」と割り切るだけでは済まされない問題でもあります。
経営陣の責任問題
今回のような大規模な再編に至った背景には、経営判断の誤りや戦略の不備があったと指摘されています。
たとえば、
- 高額な報酬を受け取りながら、抜本的な戦略転換が打ち出せなかった経営陣の姿勢
- 役員数やガバナンス体制の見直しが進まないままの組織構造
- 海外市場への依存度が高まりすぎた結果、グローバル戦略が失敗した際のリスクが顕在化
などが挙げられています。
結果的に、そのツケを現場の従業員や地域社会が背負う形となっているのは否定できません。

「社員やその家族がかわいそうだよね」

本当にその通り。支えてきたのは現場の人たちなんです。
会社が再生を目指すのであれば、まずは経営陣自身が責任の所在を明確にすることが不可欠です。
そのうえで、現場や地域との信頼関係を取り戻す努力を重ねていくことが、今後の信頼回復につながるはずです。
今後の日産に求められること
自動車業界はいま、“100年に一度”といわれる大転換期に差し掛かっています。
EV(電気自動車)への移行、カーボンニュートラルの実現、そしてAIや通信を活用したコネクテッドカーなど、技術もビジネスモデルも大きく変わろうとしています。
こうした中で日産も、従来の「ものづくり」だけでは生き残れません。
市場が本当に求める車を、持続可能な形で提供することが重要です。
実際、日産は世界に先駆けてEV「リーフ」を量産化した実績もあり、本来はこの変革期をリードする立場にある企業です。
だからこそ今こそ、企業としての軸を再確認し、信頼を取り戻すことが求められています。

「車だけじゃなく、会社としてのあり方も問われてるんだね」

“どんな車をつくるか”だけじゃなく、“どんな会社でありたいか”が見られています。
信頼回復への道
日産がこの先、再び人々から選ばれる企業となるためには、いくつかの課題をクリアする必要があります。
- 従業員の雇用に対する誠実な対応
単なる配置転換や退職募集ではなく、生活やキャリアの継続をどう支えるかという視点が欠かせません。 - 取引先企業や地域住民への丁寧な説明と支援
工場閉鎖によって連鎖的に影響を受ける企業や地域社会にも、説明責任と向き合う姿勢が必要です。 - 経営陣自身の責任と組織の透明性改革
これまでの判断に対する検証と、今後に向けたガバナンス体制の見直しも不可避です。
これらをおろそかにしたままでは、企業としての信頼は回復できません。
逆にいえば、こうしたひとつひとつの行動を丁寧に積み重ねていくことで、初めて未来に向けた新しいスタートが切れるはずです。

「厳しい時だからこそ、企業の本質が問われます」
“人を大切にする姿勢”こそが、ブランドを支える一番の土台だと思います。
今こそ問われているのは、社員やその家族、地域とどう向き合うかという覚悟。
それを示せるかどうかが、日産が次の時代を切り開けるかどうかの分かれ道となるでしょう。
まとめ
今回の追浜工場閉鎖は、単なる一工場の縮小や移転にとどまらず、日産という巨大企業の再構築に関わる重大な決断です。
- 追浜工場は2027年度末で車両生産を終了し、九州工場へ統合
- 湘南工場も2026年度中に生産を終了予定
- 背景には「Re:Nissan計画」や世界的な販売不振、巨額赤字の存在
- 約2400人の従業員の今後については、今後も協議が続く見通し
- 地域経済や下請け企業にも深刻な影響が懸念される
- 経営陣の判断や責任についても問われている
追浜工場は、長年にわたって日産の心臓部として稼働し続けてきた歴史ある拠点です。
その幕引きには、多くの人の生活、思い出、そして未来が重なっています。
この出来事は、単なる一企業の内部事情ではなく、日本の産業構造全体の課題を浮き彫りにする象徴的な出来事でもあります。
効率や利益だけでは語れない、“人”と“地域”に根ざした企業活動の在り方が、今あらためて問われているのかもしれません。

働く人、地域、そして私たちの未来に関わる大切なテーマです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考サイト