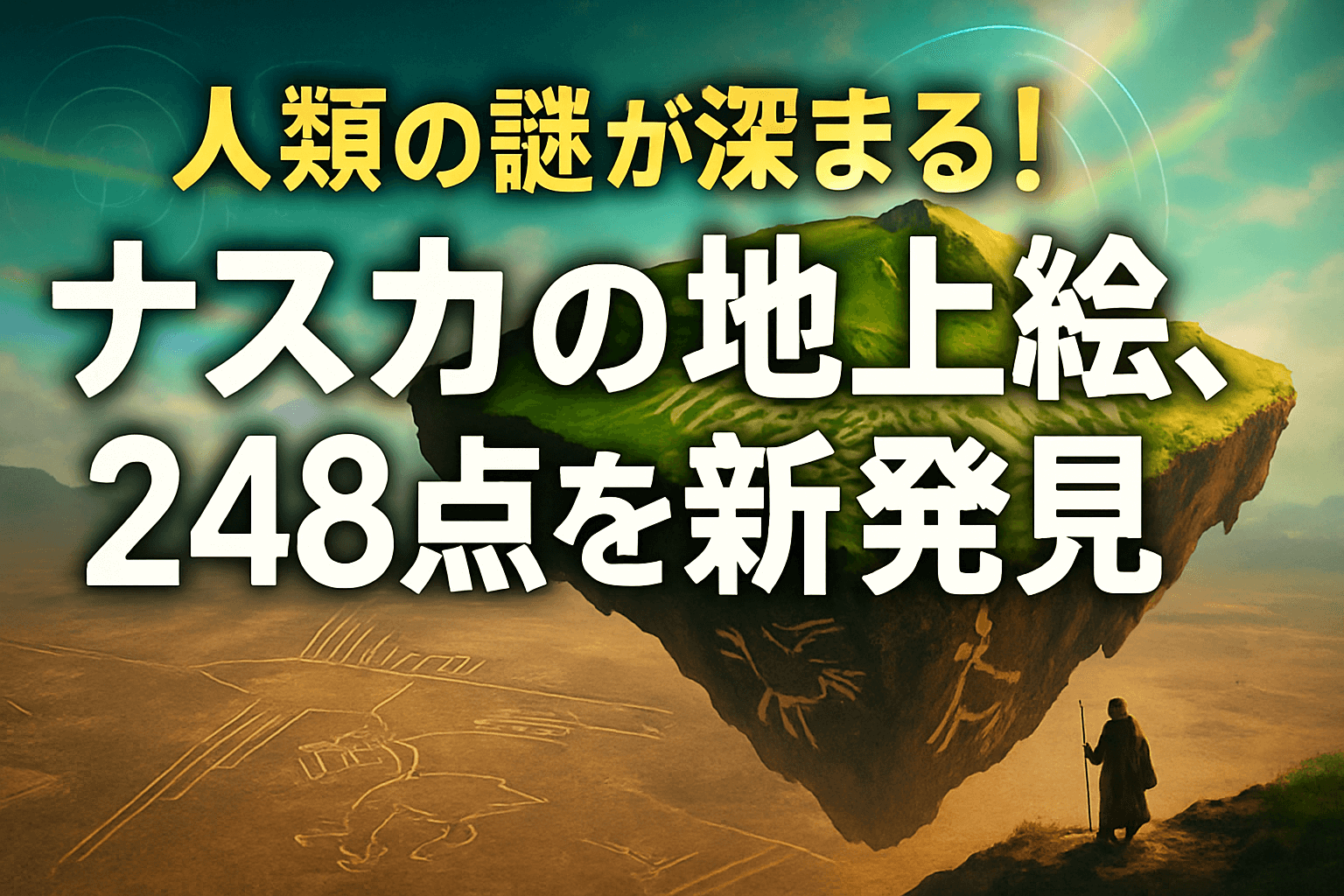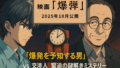2000年の時を超え、ナスカの地上絵に新たな真実が──
2000年の時を超えて、再び注目が集まる「ナスカの地上絵」。
それはまるで、遥か古代からの“メッセージ”が現代に語りかけてくるかのようです。
南米ペルーの乾燥地帯──何もないように見えるその大地には、空からでなければ見えない巨大な絵が刻まれています。
動物や人、幾何学模様など、その正体はいまだに“人類最大の謎”のひとつ。

ナスカの地上絵は、世界遺産にも登録されているんだよ!
しかも今からおよそ2000年前に描かれたとされています。
そんなナスカに、新たな歴史が刻まれました。
2025年7月28日、大阪・関西万博のペルー館で行われた記者会見にて、山形大学の坂井正人教授が驚くべき研究成果を発表しました。
なんと、AI(人工知能)を活用した調査によって、これまで確認されていなかった248点もの地上絵が新たに発見されたのです。
これにより、ナスカ地域で見つかっている具象的な地上絵は合計893点に到達。
その多くは人や動物をかたどった絵で、これまで知られていたよりもさらに多様で意味深長な構成が見えてきました。

AIが地上絵を見つけるって、ちょっと未来っぽいよね!
人間の目では気づけなかった地上絵も、AIなら見逃さないんだって。
しかも今回の研究は、「数が増えた」というだけではありません。
地上絵が描かれている“配置”や“関係性”にも注目することで、地上絵は単なる装飾ではなく、「信仰」や「記憶」をつなぐメディアだった可能性があるという、新しい仮説が浮かび上がってきたのです。
「地上絵は、私たちが思っていたよりずっと“語りかけてくる存在”かもしれない」
そんなロマンを感じずにはいられません。
そんな神秘のナスカ地上絵の歴史や特徴から、今回の発見の詳しい内容、そして“なぜ絵が消えないのか?”
という素朴な疑問まで、解説していきます。
ナスナスカ地上絵とは?歴史と特徴
ナスカの地上絵(ナスカ・ライン)は、南米ペルーの乾燥した大地に描かれた、巨大な図形や線の集合体です。
作られたのはおよそ紀元前100年から西暦800年ごろ。
この地域に栄えたナスカ文化の人々によって残されたと考えられています。
その制作方法はとてもユニーク。
地表の赤褐色の小石をどけて、下にある明るい地層を露出させることで描かれているんです。
道具や重機のない時代に、どうやってこんなに大きな図形を描いたのか…いまだに正確な方法は解明されていません。
動物や植物、幾何学模様、そして人物まで、さまざまなモチーフがあり、中には全長100メートルを超える巨大なものも。
そのスケールの大きさから、地上に立っても全体像は見えず、上空からでないと図柄が認識できないため、かつては「宇宙人へのメッセージかも?」なんて言われたこともあります。
ナスカの地上絵が幼児の落書きみたいで可愛い👶 https://t.co/ciu5j3xmcn pic.twitter.com/7Q5MzKbGqC
— チョコ (@gingastar777) July 28, 2025
🌍 1994年にはユネスコの世界文化遺産に登録され、航空写真やドローン撮影の発達とともに、世界中の研究者や観光客の注目を集めています。

ナスカの地上絵は「描いた」のではなく「削ってつくられた」んだよ!
雨がほとんど降らない乾燥地帯だから、何百年も絵がそのまま残ってるの。
🌟これまでに知られていたナスカの地上絵の代表例
- コンドル(神聖な鳥として信仰されていた猛禽類)
- 蜘蛛、ハチドリ、サルなどの動物たち
- 幾何学模様(直線、台形、渦巻きなどのパターン)
- 人間のような姿のキャラクターも一部存在
これらの地上絵には、単なるアートではない宗教的・儀式的な意味が込められていた可能性もあり、多くの研究者がその謎に挑み続けています。
山形大学が発表!248点の地上絵を新発見
2025年7月28日、大阪・関西万博2025のペルー館で、驚きの発表がありました。
ナスカ地上絵の長年の研究で知られる山形大学の坂井正人教授と、IBMのAIチームによる共同研究が、新たに248点の地上絵を発見したのです。
📅7月28日、ペルーのナショナルホリデーにあわせて
— peruatexpo (@peruatexpo) August 7, 2025
ペルーパビリオンでナスカの地上絵に関する新発見が発表されました🌀… pic.twitter.com/6aJhFrXo05
この調査は、2023年〜2024年にかけて実施されたAI支援の現地フィールドワークの成果。
広大なナスカ台地を対象に、人工知能が衛星画像や空撮データをもとに“人の目では気づきにくい地上絵”を検出し、それを人間の専門家が検証するというハイブリッドな方法で進められました。

AIは、大量の画像を高速で処理できるから、広いナスカ台地の調査にピッタリなんだって!
しかも、人間より早く“線の違和感”を見つけられることもあるんだよ。
では、実際に見つかった248点の地上絵には、どんなものが含まれていたのでしょうか?
以下は、その内訳です。
📊発見された地上絵の内訳
- 人物像:41点
- 斬首された人物像:31点
- リャマ(アンデス地方の家畜):21点
- 猛禽類やその他の動物:66点
- 幾何学模様(線、渦巻き、台形など):81点
- その他:7点
このうち、人物や動物などの“具象的地上絵”が160点を占めており、今回の発見によって、ナスカ台地でこれまでに確認された具象的な地上絵の総数はなんと893点に!
特に注目されているのは、斬首された人物の地上絵。
これは、ナスカ文化における生贄や儀式、死生観に関する新たな手がかりになる可能性があり、専門家の間でも今後の分析が期待されています。
このように、単なる“数の増加”ではなく、ナスカの人々が何を信じ、どんな社会を築いていたのか──その「内面」に迫る発見でもあるのです。
AIと考古学の融合で解明されるナスカの秘密
今回の大発見は、決して偶然や「なんとなく見つかった」というものではありません。
最先端のAI技術と、長年ナスカを研究してきた考古学者たちの“知恵と経験”がタッグを組んだことで実現したのです。
このプロジェクトを進めたのは、山形大学とIBMが共同開発したAI分析システム。
AIにはあらかじめ、過去に見つかっている地上絵の形や特徴を大量に学習させ、“地上絵っぽい”パターンを画像の中から自動で見つけ出せるように訓練しました。

AIは「たくさん覚える」だけじゃなくて、「これ地上絵っぽい!」と判断できるんだよ。
今は考古学者とAIがタッグを組む時代なんだね。
その結果、AIは数百点の“地上絵かもしれない”候補を自動で抽出。
それをもとに、研究者たちが現地を一つひとつ歩いて確認し、本物の地上絵であるかどうかを丁寧に検証していきました。
🔍AIによる調査フロー(ざっくり解説)
- 高解像度の航空写真や衛星画像をAIに学習させる
- 地上絵の特徴パターンを認識・分類
- 地上絵候補を数百点自動抽出
- 研究者による現地踏査で実物を確認
このようにして、248点の新しい地上絵が“確定”されたわけです。
さらに注目すべきは、現在もAIが検出した「未確認の候補地」が500点以上あるということ。
つまり、まだまだ新しいナスカ地上絵が見つかる可能性は十分あるんです。
「人類の謎」は、テクノロジーの力で少しずつその姿を現しはじめている──。
そんな時代に私たちは生きているのかもしれませんね。
新発見の地上絵が示す“物語性”とメッセージ
今回の発見の中でも、特に注目されたのが、新たに見つかった地上絵の“配置”にまつわる事実です。
なんと、これらの地上絵はただバラバラに描かれていたわけではなく、“テーマごと”にグループ化され、特定のルートや小道に沿って並んでいたことが分かってきました。
つまり、そこには偶然ではなく、何らかの意図的な「並び順」や「構成」があった可能性が高いのです。
🌿テーマ別の地上絵の例
- 「人身供儀」:斬首された人物と神官の姿を組み合わせた地上絵
- 「野生の鳥」:翼を広げたタカやコンドルなどの猛禽類
- 「家畜と農耕」:リャマ、トウモロコシ、キツネなど、生活に密接した存在が同じ場所に描かれているケースも

地上絵ってバラバラにあると思ってたけど、テーマごとに集まってるの?

実はナスカの地上絵の多くは「古代の道」に沿って描かれているんだよ。
もしかしたら、昔の人たちはその道を歩きながら、物語や祈りを“体感”していたのかもね。
このように、テーマ別に配置された地上絵たちは、ただの巨大アートではなく、当時の人々が信仰や伝承を伝える“語りの場”だった可能性を私たちに示しています。
坂井正人教授も「地上絵は巨大なメディアだった可能性がある」と述べ、複数の地上絵が組み合わさることで、宗教的な儀式や神話、共同体の記憶を描いていたのではないかと分析。
ナスカの地面に描かれたこれらの絵は、「言葉」や「文字」の代わりに、人々の信仰や歴史を伝える“ビジュアルストーリーテリング”だったのかもしれません。
かつては“謎の絵”とされていたナスカの地上絵。
それが今、「古代人の心を映し出すメッセージ」だったのではないか──そんな新しい見方が生まれ始めているのです。
なぜナスカの地上絵は消えないのか?その理由に迫る
約2000年ものあいだ、風や雨にさらされながらも、不思議なほど鮮明に残り続けているナスカの地上絵。
「どうして消えずに保たれてきたの?」と思う方も多いのではないでしょうか。
この“奇跡の保存状態”には、実はいくつもの自然の条件と、人々の努力が関係しています。

ナスカって、雨がほとんど降らないし風も優しいから、砂が動きにくいんだよ。
それに地面がカチカチで崩れにくいのもポイントなんだって!
では、ナスカの地上絵が長い年月を経ても消えなかった理由を、もう少し具体的に見ていきましょう。
☀️保存され続ける5つの理由
- 年間降水量わずか4mmという超乾燥地帯
→ 雨がほとんど降らないため、水による侵食や流出が起きにくい。 - 適度に吹く風が砂の堆積を防ぐ
→ 強すぎず、弱すぎない風が砂の積もりすぎを防ぎ、絵を見えやすく保ってくれる。 - 地表が硬く、地上絵が踏み荒らされにくい
→ 硬い大地のため、人や動物の足跡が残りにくく、絵が消えにくい構造になっている。 - 野生動物による損傷がほとんどない
→ 砂漠のような乾燥地帯で生き物の活動が少なく、地上絵が傷つきにくい。 - 現地の人々や研究者による保護活動
→ ユネスコの世界遺産に登録された1994年以降、保全の取り組みも本格化し、風化を防ぐ努力が続けられている。
さらに特筆すべきは、地質に含まれる「硫酸カルシウム(石膏)」の存在。
この成分が雨や夜露と反応して自然な“固結作用”を生み出し、表面の石や砂を固めてくれるのです。
まさに、ナスカは地上絵が“自らを守る力”を持つ奇跡の土地と言えるでしょう。
自然の条件と、人の想いと、偶然のバランスが奇跡的に重なって――。
それがナスカの地上絵が今なお私たちに語りかけてくる理由なのかもしれません。
固結作用を生み出しており、描かれた地上絵が自然に保存される“奇跡の土地”ともいえるのです。
地上絵を未来へ守るための取り組み
人類の遺産とも言えるナスカの地上絵。
でも、このまま自然に任せていては、風や砂、時間の経過によって徐々に失われてしまうリスクもあるのです。
現在、ナスカの地上絵の多くは、ペルー政府によって「ナスカ地上絵保護公園」として管理され、ユネスコ世界遺産にも登録されています。
しかしそれでも、完全な保護は難しく、風化や破損といった課題は今なお続いているのが現実です。

ナスカの地上絵は広大すぎて、現地の保護にも限界があるんだ。
だから、世界中の人たちの協力がカギなんだね。
そこで今、地上絵を守るための新たな取り組みが進められています。
そのひとつが、山形大学とペルー・ナスカ市によるクラウドファンディングです。
このプロジェクトでは、2025年9月20日まで寄付を受付中で、集まった資金は以下のような活動に使われる予定です
- 地上絵の調査と記録保存
- 地上絵を守るための保全作業や補修
- 地元や世界の人々に向けた展示・教育活動
支援はこちら:地上絵を守るクラウドファンディング(readyfor.jp)
さらに現地では、日本の支援によって新たな展望台の設置も進んでおり、観光と保護を両立させながら、地上絵の価値を次世代に伝える取り組みが広がりつつあります。
ナスカの地上絵は、ただ守られるものではなく、「受け継いでいくもの」として、今この瞬間も世界中の人たちの手で支えられているのです。
ペルー館で展示中!現地でのナスカ体験情報
もしあなたがナスカ地上絵の“今”を体感したいなら、大阪・関西万博2025のペルー館は必見です!
現在(〜10月13日まで)、今回の研究成果を反映した特別展示イベントが開催されています。
山形大学、ナスカの地上絵248点発見 大阪万博ペルー館で成果披露https://t.co/mfIaV3W0Yw
— 日経関西 (@nikkeikansai) August 2, 2025
AIを使った画像解析などで地上絵と思われる場所を特定しました。地上絵候補には、未調査のものが500点以上残っています。今後の現地調査で、地上絵かどうかの確認作業を進めていきます。#大阪・関西万博 pic.twitter.com/p5Q6natK8A
今回の展示では、AI技術と考古学の融合によって明らかになったナスカの新たな魅力が、五感で楽しめるようになっています。

ペルー館は「ナスカ地上絵と古代文明の魅力を伝える」ことをコンセプトにしてるよ。
最新研究も紹介されてて、学びと体験が両立してるんだ。
ペルー館・注目の展示内容
- 最新発見のパネル展示
→ AIで新たに確認された地上絵の図解や調査写真を、わかりやすく解説付きで展示 - 土器・装飾品などの実物展示(日本初公開あり)
→ 古代ナスカ文化の生活道具や儀式に使われた品々を間近で見られる貴重な機会 - AI調査のドキュメンタリー映像
→ 山形大学とIBMがどのように地上絵を探し当てたのか、映像で臨場感たっぷりに紹介 - 伝統ダンス&ペルー料理の体験イベント(7月28日開催済)
→ 地元の舞踊や音楽に触れながら、ナスカの文化を味覚と聴覚でも体験
🌎ちなみに…
ペルー料理は、なんと12年連続で「世界最高のグルメ観光地」に選ばれているって知っていましたか?
地元の食材や味付けにも、古代ナスカの知恵や文化が息づいているんです。
展示は10月13日までの期間限定。
「見る・学ぶ・感じる」が一体となったナスカ体験を、ぜひ現地で楽しんでみてくださいね!
まとめ:ナスカ地上絵はメッセージか、記憶か、それとも…
ナスカの地上絵は、現代のAI技術と考古学が出会ったことで、今、再び注目を集めています。
今回、山形大学とIBMの共同研究チームが新たに248点を発見したことで、これまでに確認された具象的な地上絵の総数は893点となりました。
これまで、ナスカの地上絵は
「なぜ作られたのか?」「誰のために?」という大きな謎に包まれてきました。
ですが、今回の研究では、特定のテーマごとに配置されていたという新たな視点が加わり、地上絵がただのアートではなく、
共同体の信仰や儀式、記憶を継承する“語りのメディア”だった可能性
が示唆されています。
科学の進歩が、2000年前の人々の想いに触れるきっかけを与えてくれる──。
そんなロマンが、今回の発見には込められているように思います。
ナスカの地上絵は、人類の“記憶”なのか、それとも“未来へのメッセージ”なのか──。
それを解き明かす旅は、まだ始まったばかりです。
私たちができることは、この貴重な文化遺産を守り、後世へつないでいくこと。
「この地球には、まだ私たちの知らないことがたくさんあるんだ」と。
これからもワクワクする世界の“今”を一緒に追いかけていきましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!