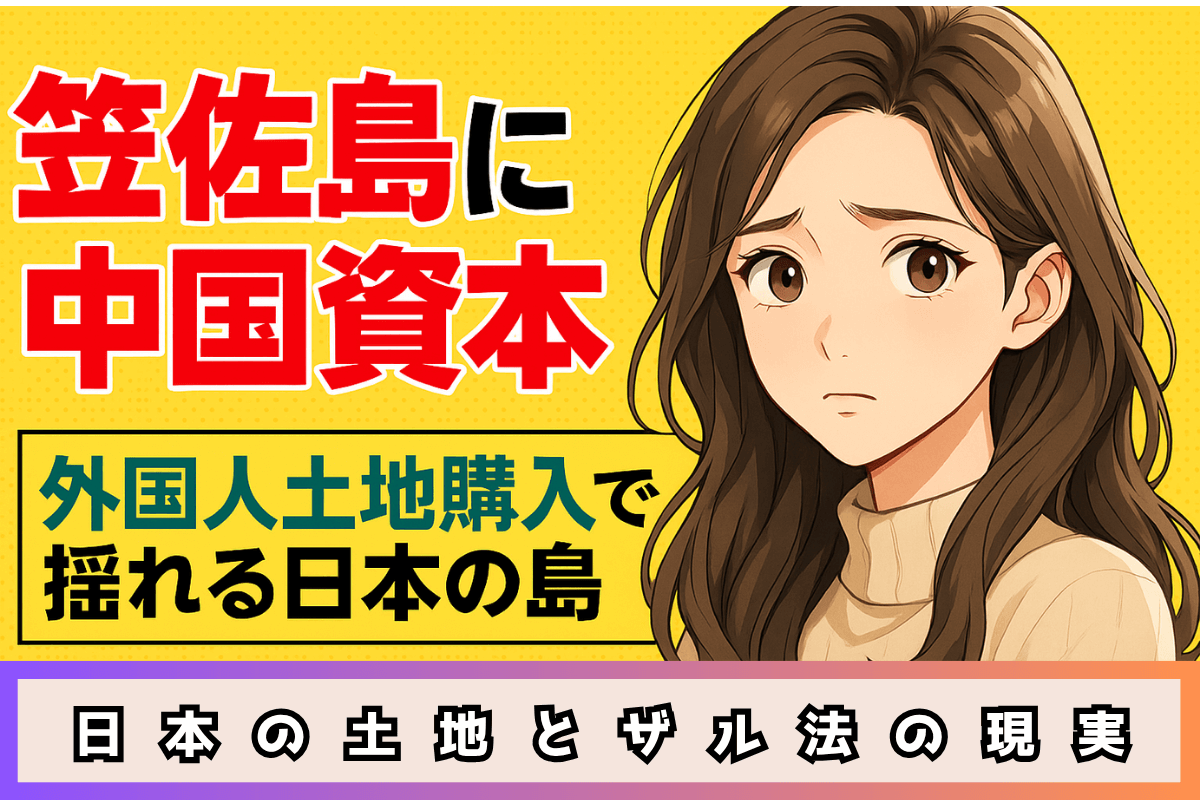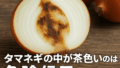静かな島に忍び寄る変化
穏やかな海に囲まれた瀬戸内海の小さな島・笠佐島(かささじま)。
山口県に位置するこの島は、かつて数世帯がひっそりと暮らす、いわば“知られざる離島”でした。
しかし近年、この静寂に包まれた島が、外国資本による土地買収でにわかに注目を集めています。
特に報じられているのが、中国資本による土地取得。
一部報道では「島の一部が丸ごと買われた」との話もあり、島民の間には不安の声が広がっています。

別荘を建てるだけなら別にいいんじゃないの?」

実際、観光や移住の目的で土地を買う人もいます。
でも、問題はそこだけじゃないんです…。
こうした土地取得には、単なる不動産の話にとどまらない、日本の法制度の甘さや安全保障に関わる深刻な問題が潜んでいます。
静かで平和な島で、いま何が起きているのか。
そして、それは日本全体にどんな影響をもたらすのか──。
笠佐島とはどんな島なのか、そしてなぜ今「外国人に買われる島」として注目されている理由をお伝えしていきます。
笠佐島とは?その特徴と現状
山口県の瀬戸内海に浮かぶ笠佐島(かささじま)は、周防大島の小松港から西へ約2キロ、船でわずか10分ほどの場所に位置しています。
島の面積はおよそ94万平方メートル。
東京ドーム約20個分の広さがありながら、現在の島民はわずか5世帯7人という、とても静かな島です。
定期船が1日3~4便、本土との間を往復しているものの、それ以外にアクセス手段はなく、観光地としても大きく知られていません。
それゆえ、長らく“忘れられた島”とも言われてきました。
そんな笠佐島に、ここ数年ゆるやかな変化の兆しが見え始めました。
島を横断する林道の整備、新しい電柱の設置など、インフラの改善が少しずつ進んでいるのです。
外から見ると、観光や移住を見据えた開発が始まったかのようにも見えますが、その背景には外国資本の動きが関係している可能性が浮かび上がってきました。
実際に、中国人による土地購入が報じられたのをきっかけに、土地を下見に訪れる外国人の姿も確認されています。
かつては人影もまばらだった島に、異国の言葉が響く場面が少しずつ増えてきているのです。
このように、静かで手つかずの自然が残る離島が、外国資本にとって“お買い得”な投資先となっている現実があります。
一見するとのどかな風景の裏側で、確実に“誰かの所有地”が増えつつある――そんな変化が、今の笠佐島で起きているのです。
実際にどれくらいの土地が外国人に取得されているのか、そしてその動きがどのように進んでいるのかを詳しく見ていきます。
中国人による土地取得の実態
実際に、笠佐島で外国人によって購入された土地は、すでに登記上で確認されています。
登記簿によれば、中国籍の人物が取得した土地は、合計で約3,651平方メートル。
島全体の面積から見ればごく一部に過ぎないものの、その動きには注目が集まっています。
購入したのは、中国・上海に住む親日家の中国人男性と、その関係者3人。
取引の経緯について、不動産業者は次のように説明しています。
「分譲情報をネットで見た男性から最初に問い合わせがありました。
その後、何度も中国に足を運んで商談を重ねた結果、正式に契約がまとまりました」
つまり、個人の関心から始まった買収ではあるものの、綿密な計画と交渉の末に成立した取引であることがわかります。
単なる観光目的ではなく、ある程度の“意図”が感じられる動きだと言えるかもしれません。
さらに現地では、工事用重機の搬入や、新たに設置された電柱の存在が確認されています。
所有者が「桟橋を建設したい」と話していたことも伝えられており、インフラの整備を進めようとする意思がうかがえます。

「たった数筆の土地を買っただけで、そんなに大げさに騒ぐこと?」

でもその土地、実はすごく重要な場所なんです…!
実はこの土地が、海上自衛隊・呉基地にも近接する“戦略的に重要なエリア”に位置しているのです。
呉基地は、日本の海上防衛の中でも中核を担う拠点のひとつ。
その付近に外国人が所有する土地ができるということは、国防上の懸念を抱かざるを得ません。
笠佐島は小さな島ですが、位置的には広島県の軍港エリアと目と鼻の先。
だからこそ、一部の土地が外国人の手に渡ったというだけでも、大きな意味を持つのです。
このような動きが他の離島でも起こりつつある今、「今回はたまたま」では済まされない現実が日本各地で浮かび上がっています。
なぜ日本の土地が外国人にとって魅力的なのか、その背景を深掘りしていきます。
なぜ日本の土地が外国人に人気なのか?
実は、中国人による日本の土地取得は今回の笠佐島が初めてではありません。
例えば2020年には、沖縄県の屋那覇島で島の約51%が中国人の手に渡ったことが報じられ、全国的なニュースになりました。
また、北海道のリゾート地・ニセコ町も、近年は外国資本による土地購入が加速している地域のひとつです。
このように、日本の土地が外国人にとって魅力的な「投資先」や「別荘地」として注目されている背景には、いくつかの明確な理由があります。
● 外国人にとって日本の土地が人気の主な理由
① 円安の影響で“割安”に見える
特に近年、円安傾向が続いているため、海外から見ると日本の不動産が「お得」に見える状況が続いています。
同じ金額でも、自国で買える土地より広くて質が良い土地が手に入るケースもあるのです。
② 他国と比べて購入規制が非常に緩い
日本では外国人が土地を購入することにほとんど制限がないという点も大きな魅力のひとつです。
これは、国際的に見ると珍しい制度であり、例えば中国やフィリピン、タイなどでは外国人による不動産取得に厳しい制限や制約が設けられています。
③ 投資対象としての“利回り”が良好
都心部のマンションや観光地の別荘などは、民泊や賃貸運用によって高い収益が期待できるため、“投資目的”で購入する外国人も増えています。
④ 土地の“用途制限”が少ない
日本では、都市計画区域外や一部の地方では、建物の用途や形状に関する制限が少ないため、思い通りの使い方ができる自由度の高さも評価されています。

「日本って、外国人でも簡単に土地が買えるの?」

実は、日本では国籍に関係なく誰でも土地を自由に購入できるのが現状です。買った後の用途にも、基本的に大きな制限はありません。
こうした背景があるため、笠佐島のような離島や山間部、観光地などでも、外国人による土地取得が進んでいるのです。
魅力的な自然や静かな環境が残る土地ほど、“将来価値”を見込んで買われていく傾向があります。
しかし、その結果として何が起こるのか──
こうした土地取得が日本の安全保障や国益にどう関わるのかについて考えていきます。
安全保障上のリスクと笠佐島の重要性
一見のどかで静かな笠佐島ですが、実は単なる田舎の島とは言い切れません。
その地理的な位置には、日本の安全保障に関わる重大な意味があるのです。
というのも、笠佐島の周辺には、海上自衛隊の呉基地や、米軍岩国基地といった日米の重要な防衛拠点が点在しています。
また、瀬戸内海そのものが、国内外の商船や軍艦が行き交う海上交通の要衝であり、万が一有事が起きた場合には、非常に戦略的な地域となります。
つまり、そのエリアに存在する“誰が所有しているかわからない土地”が安全保障上のリスクになりうるということです。
● 外国資本が抱える“見えないリスク”
特に注目されているのが、中国の法律との関係です。
中国では、「国家情報法」や「国防動員法」といった法律により、民間人や企業が国家に協力する義務が定められています。
たとえば有事の際、中国政府が
- 中国籍の民間人に情報提供を命じる
- 海外にある中国人の不動産や設備を徴用する
といった対応を取る可能性が、法的に否定できない仕組みとなっています。
.png)
「島がドローン基地や監視拠点になるかもって、本当?」

“絶対にない”とも言い切れないのが現実です。
現に、世界では国家の戦略に民間を巻き込むサイレント戦術が進行しており、特に土地やインフラの“所有”そのものが安全保障の一部とみなされる時代になっています。
そう考えると、瀬戸内海という日本の中枢に近い場所で、誰がどの土地を所有しているかという点は、決して見過ごすことのできない重要な要素なのです。
では、なぜこうした外国人による土地取得が法的に止められないのか?
その根本的な原因である、日本の法制度の“盲点”と言われていることはどんなことでしょうか。
日本の法制度の盲点と課題
日本には、外国人による土地取得を直接的に規制する明確な法律がほとんど存在していません。
2022年にようやく施行されたのが「重要土地等調査法」ですが、これもあくまで“調査”を目的とした法律です。
この法律は、防衛施設や原子力発電所など、安全保障上重要な施設の周辺1キロ圏内の土地を「注視区域」「特別注視区域」に指定し、利用実態を調査するというもの。
しかし、実際に売買そのものを禁止したり強制的に止めたりすることはできないため、現場では「実効性に乏しい」との指摘もあります。
このような背景から、専門家や国会議員の間では「ザル法(ザルのように穴だらけの法律)」と揶揄されることも少なくありません。
● 海外では土地購入に厳しい規制も

「日本って、やっぱり外国人に甘いの?」

たしかに、日本は“買いたい放題”に近い状態かもしれません…。
実際、他の先進国と比べると、日本の土地取得規制はかなり緩やかです。
たとえば
- ニュージーランドでは、2018年以降、外国人による住宅用不動産の購入を原則禁止
- オーストラリアでは、購入前に政府の許可が必要で、用途によって厳しい審査が行われます
- 中国やフィリピンなどでは、外国人による土地所有が法律で禁止されているか、著しく制限されています
一方、日本では、国籍に関係なく誰でも土地を購入可能。
しかも、所有後の用途についてもほとんど制限がないというのが現実です。
● なぜ、こうした状況が続いているのか?
背景には、以下のような要因があると考えられています
- 「経済自由主義」や「外資誘致」の名のもとに、規制強化が後回しにされてきた
- 戦後の憲法や法制度が「私有財産の保護」を重視している
- 地方の過疎化が深刻化し、「買ってくれるなら誰でもありがたい」という空気がある
こうした事情が絡み合い、国家的な安全保障と個人の財産権のバランスが取れていない状態が続いているのです。
小さな島の一筆の土地が、実は国の根幹を揺るがす火種になるかもしれない――
そんな可能性が現実となりつつある今、制度の見直しが求められていることは間違いありません。
地元住民と専門家が感じる懸念
外国資本による土地取得のニュースが広まる中、笠佐島の周辺では、住民の間に静かな不安が広がっています。
地元の船長は、「最近、高級車に乗って島を訪れる中国人をよく見かけるようになった」と証言。
少し前までは滅多に人が来なかった静かな島に、“見慣れない人”が頻繁に訪れるようになったことに戸惑いを隠しません。
また、地方自治体の関係者からは、
「このまま土地が次々に買われていったら、いずれ島全体が乗っ取られてしまうのではないか」
という、切実な危機感も聞こえてきます。

情報が少ない分、逆に不安だけが大きくなってしまうんです。
● 売らざるを得ない“構造的な負担”
この問題には、地元住民の意志とは無関係に土地を手放さざるを得なくなる“見えない圧力”も存在します。
不動産や税制度に詳しい専門家は、次のような問題点を指摘しています。
① 地価の上昇による税負担の増加
外国人による購入や開発計画で土地の価値が一気に上がると、課税標準額も上昇します。
その結果、固定資産税などの負担が跳ね上がり、年金や限られた収入で暮らす島民には大きな重荷になります。
② 登録免許税・不動産取得税の負担
土地を相続・譲渡・維持する際には、複数の税金がかかります。
特に登録免許税や不動産取得税といった一時的な負担も大きく、手続きを諦めて“売却してしまう”選択をする人が増えるのです。
③ 管理コストの上昇と「空き地化」の進行
離島ゆえの管理の手間や交通費も加わると、「土地を維持するだけで損をする」という状況になってしまい、結果として“外国資本に売却する”以外の選択肢がなくなるケースも珍しくありません。
こうした状況は、島民の意思というよりも「構造的に土地を守れなくなる仕組み」が問題といえます。
つまり、“売りたい”のではなく、“売らざるを得ない”人たちが増えている――。
この流れを放置すれば、今後ほかの離島や過疎地にも同じような波が押し寄せる可能性があります。
今後必要とされる対策とは
ここまで見てきたように、外国資本による土地取得の問題は、単に売買の話にとどまりません。
安全保障・地域経済・地元住民の暮らしに深く関わる課題であり、いまや全国規模で考えるべきテーマとなっています。
そのため、「調査だけで終わる法整備」では不十分であり、より実効性のある対策が求められます。
● 急務とされる5つの対策
① 外国人による土地取得に対する「事前審査制度」の導入
現在の法律では、購入後に調査や届出が行われる仕組みのため、「買った後では遅い」という声も出てきています。
そのため、購入前に審査を義務づけ、安全保障上の懸念があれば拒否できる制度が欲しいところです。
② 即時施行型の法規制で「駆け込み購入」を防ぐ
法改正の報道によって、施行前に“駆け込み購入”が起きる可能性が懸念されています。
それを防ぐためにも、法律の公布と同時に効力を持つ「即時施行型」の規制が望まれる場面もあるかもしれません。
③ 用途やエリアごとの「目的制限」
軍事施設周辺や国境離島、重要インフラ地域など、エリアごとに土地利用の影響は異なります。
そのため、使用目的に応じて購入を制限するガイドラインが検討されてもよいように思われます。
住宅・観光・農地などの用途別にルールを分けることで、安全保障と経済活動のバランスもとりやすくなるのではないでしょうか。
④ 「相互主義」の原則に基づく取得制限の検討
たとえば中国では、日本人が自由に土地を購入することは難しいとされています。
そうした現実を踏まえると、日本でも「相互主義」に基づいて土地取得に制限を設けるという選択肢もあってもいいように思います。
一部の国に限った取得制限についても、今後議論の的になる可能性は十分ありそうです。
⑤ 日本人が土地を守れる「税制の見直し」
地価が上がることで固定資産税などの負担が大きくなり、結果的に地元住民が土地を手放さざるを得ないというケースもあります。
「売らずに持ち続けることが損にならない」制度を整えることが、地域の持続性につながると感じられます。
たとえば税軽減措置や補助制度の検討なども、1つの方向性かもしれません。

「ただ規制するだけじゃなくて、日本人が安心して自分の土地を守れる制度もあると嬉しいですね。」
“守る力”と“持ち続ける力”、両方がそろってこそ、地域の未来はより安定するのかもしれません。
今後の日本に求められるのは、一方的に“外国人排除”の方向に進むことではなく、自国の資源や安全を守りつつ、国際社会とも共存できるバランスの取れた制度設計です。
笠佐島の事例は、その「第一歩」として、私たち一人ひとりが考えるべき問いを投げかけています。
“買われる島”のままでいいのか? それとも、“守るための仕組み”をつくっていくのか?
おわりに:私たちは何を守るべきか
笠佐島で起きている中国資本による土地取得は、単なる地方の小さな島の話ではありません。
これは、日本各地で起こり得る“国境なき土地買収”の最前線にほかなりません。
現在の日本では、外国人が土地を購入する際の規制がほとんど存在しないため、法の“隙間”を突くような取引が次々と進んでいます。
今回のように、防衛拠点に近い場所や離島といった安全保障上の要所までもが対象となりうるのです。

「問題があるなら、国が止めればいいのに…?」
確かにそう思われるかもしれません。
しかし現行の「重要土地等調査法」は、あくまで“調査”が目的で、売買自体を制限するものではありません。そのため、実効性に乏しく「ザル法」とも言われています。
一方で、地元の人々が島の土地を手放す背景には、過疎化や税負担の重さといった現実的な課題もあります。
売却が“悪”なのではなく、制度として“守る手段”が整っていないことが問題なのです。
日本人が日本の土地を守るためには、以下のような視点が今後ますます重要になるでしょう。
- 外国人による土地取得の透明性を高める制度づくり
- 土地売買の「目的」や「場所」による規制強化
- 地方の土地所有者を支える仕組みと税制見直し

「土地を売る・守る、その選択が未来の日本を左右するかもしれません。」
この問題を単に「外国人vs日本人」という対立構造で語るのではなく、私たち一人ひとりが“何を未来に残したいのか”を考えるきっかけにしていくことが大切です。
日本の土地は、単なる資産ではなく、文化や安全、暮らしの土台です。
それをどう守るかは、私たちの選択にかかっています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考サイト