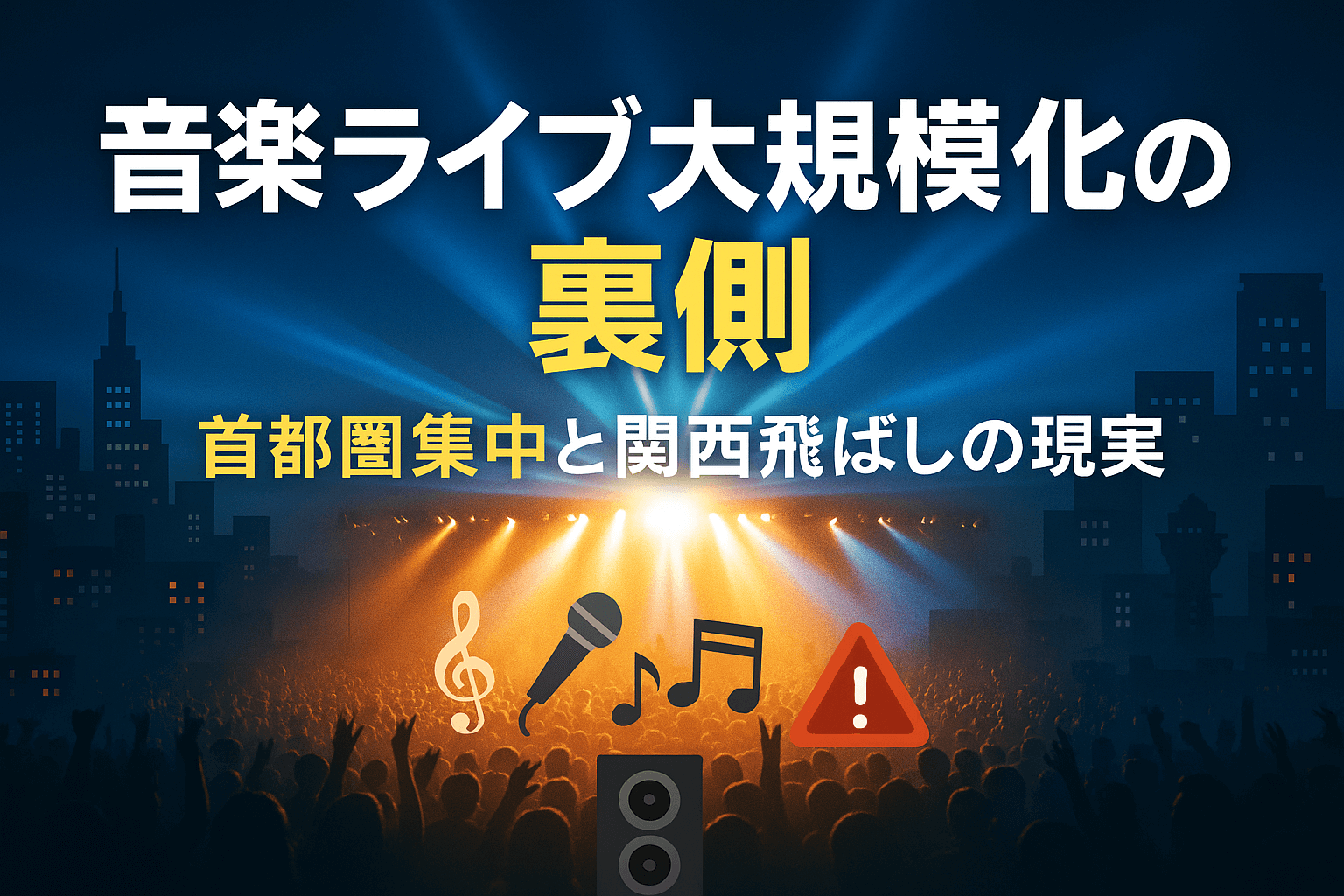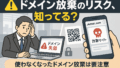音楽ファン必見!ライブの開催地が「東京ばかり」になっているワケ
「最近、大物アーティストのライブが東京ばかりで、大阪には来てくれない…」
そんな声を関西の音楽ファンから耳にすることが増えていませんか?
2024年、日本の音楽ライブ業界は大きな転換期を迎えています。アリーナ規模の大規模公演が急増する一方で、地方公演、とりわけ“関西”でのライブ開催が減少傾向にあるのです。
その現象は業界関係者の間で**「関西飛ばし」**とまで呼ばれるように。
なぜこのような事態が起こっているのでしょうか?
この記事では、音楽ライブの首都圏一極集中の実情と背景、そして関西の音楽文化を守るためにできることを、データとともにわかりやすく解説します。
アリーナ公演が増加、ホール公演は減少へ
規模の拡大と収益性の両立が進む
2024年、アリーナクラスのライブ公演は過去最大の規模で行われました。
一般社団法人コンサートプロモーターズ協会(ACPC)によると、
- アリーナ公演の入場者数:2,189万人(前年より520万人増)
- ホール公演の入場者数:1,621万人(前年より200万人減)
このデータからも、アーティストや事務所が大きな箱で効率的にライブを行う傾向にあることが分かります。

「多くの人に届ける」と「採算を取る」を両立するには、大規模会場の方が有利!
首都圏に新アリーナ続々!東京偏重が止まらない理由
近年、音楽ライブやイベントの舞台となる大型アリーナが、首都圏で次々と誕生しているのをご存じでしょうか?
特に目立っているのが、東京都心やその周辺エリアでの“新アリーナ建設ラッシュ”。
最新設備を備えたライブ会場が一気に増えており、音楽業界全体にも大きな影響を与えています。
🌟 代表的な新アリーナをチェック!
- Kアリーナ横浜(収容約2万人):2023年開業。音響や視界にこだわった「ライブ特化型」会場として話題に。
- ららアリーナ東京ベイ(収容約1万人):2024年開業。大型商業施設併設でアクセスも抜群。
この5年間で、なんと首都圏にだけで6つの新アリーナが建設されており、これは他の地方と比べても圧倒的な数です。
🎤 首都圏にライブが集中するワケは?
こうしたインフラ整備の結果、全国で開催されたアリーナ公演のうち約25%(640公演)が首都圏で行われています。
4分の1が東京やその周辺に偏っている計算です。

最新設備と演出の自由度が高い新アリーナは、アーティスト側にとっても魅力的な舞台。
より高品質なライブを届けたいと考えると、自然と“東京中心”になりがち。
🎟 有名アーティストの公演スケジュールにも変化が?
たとえば2024年6月には、B’zがKアリーナ横浜で2週連続公演を開催。
ほかにも竹内まりやのライブ開催が予定されるなど、話題性のあるイベントが首都圏に集中。
全国のファンが“東京詣で”をする状況も生まれており、
一部では**「関西や地方を飛ばすツアースケジュール」**も珍しくなくなってきています。
⚠️ 東京開催が増える=地方ファンの負担が増加!

交通費や宿泊費など、“推し活遠征”がますますハードルの高いものになっているという声も…。
関西飛ばしの実態と懸念
首都圏の新アリーナ建設ラッシュに伴い、「関西飛ばし」問題がますます注目を集めています。
近年、大規模なツアーやライブイベントが「東京中心」になり、関西を含む地方公演が減ってしまうケースが増加中です。
🌟 業界団体も異例の声明を発表
2024年2月には、コンサートプロモーターズ協会(ACPC)の関西支部が、なんと公式に危機感を表明しました。
「このまま一極集中が進行した場合、『大型公演の関西飛ばし』が更に加速することは間違いなく、関西のエンタメの衰退を危惧する」

こうした公式コメントが出るのは、業界としても極めて異例なことみたいです。
つまり「関西飛ばし」は単なるファンの不満ではなく、音楽業界全体が直面している深刻な構造的課題だと認められつつあるわけですね。
🎤 関西の音楽文化への影響は?
実際、関西は長年にわたり日本の音楽シーンを支えてきた土地柄です。
大阪城ホール、京セラドーム、神戸ワールド記念ホールなど歴史ある会場も多く、アーティストにとっても重要な舞台でした。
しかし首都圏に最新鋭のアリーナが集中することで、
- より演出が自由な東京会場を優先するツアー日程
- 地方スケジュール削減によるコスト最適化
といった流れが加速。
結果として、関西ファンがライブを見られる機会は減りつつあります。
⚠️ このまま放置すると…
この「一極集中」が進めば進むほど、関西のエンタメ市場そのものが縮小しかねません。
地元経済や文化振興にも大きな影響を与えるため、ファンだけでなく自治体や業界全体での議論が必要になっているのです。
なぜ関西でなぜ関西でライブが開かれにくくなっているのか?
「ハコ」が足りない?首都圏と関西の会場格差
まず、最も大きな理由のひとつが会場(ハコ)の数と質の違いです。
関西には「大阪城ホール」や「丸善インテックアリーナ大阪」など、音楽ファンにとって馴染みの深いアリーナが存在します。
ただし、これらの施設は1980年代〜90年代に開業したものが多く、最新の音響設備や演出機材への対応力では、どうしても新設アリーナに一歩譲る部分があるのが現状です。
首都圏では2020年代に入ってからも、Kアリーナ横浜やららアリーナ東京ベイなど、次々と新しいライブ専用施設が誕生しており、アーティスト側にとっては「演出の自由度が高い」「映像収録にも向いている」などの理由から、開催地として選ばれやすい状況が整っているんです。

新しい会場ほど“映える”ライブが作れる=選ばれる確率もアップ!
公演日が取りづらい…スケジュール確保の難しさ
また、スケジュール面の問題も見逃せません。
首都圏ではアリーナの数が多いため、日程の選択肢が広く、ツアー全体のスケジューリングもしやすいのが強みです。
一方で、関西では「大規模な公演に対応できる会場が少ない」ことから、すでにイベントで埋まっていて希望日が取れないというケースが頻繁に発生していると言われています。
その結果、「行きたいけど日程が合わない」「アーティストが来るタイミングが極端に少ない」といったファンの声なきストレスにもつながってしまいます。
実はコストも高い?地方開催の“見えない負担”
さらに、アーティストや制作サイドからよく挙がるのがコスト面の負担。
関西でライブを開催する場合、首都圏に比べて機材やスタッフの移動が必要になり、それに伴う運搬費・人件費・宿泊費などが加算されます。
これらのコストが想像以上に重くのしかかり、「予算内に収めるには開催地を絞らざるを得ない」という選択に繋がることも。
もちろん、関西にファンが多いアーティストも多くいますが、“コスパの良さ”というビジネス判断がツアー構成に大きく影響するのは避けられない現実です。

アーティストにとって“関西開催=割高”と思われてしまうのは大きな課題…。
このように、**「ハコの質」+「スケジュールの確保しづらさ」+「コスト問題」**という3つの要因が重なって、「関西飛ばし」が生まれてしまっているのです。
それでも関西に希望はある!新たなアリーナ建設計画に注目
「関西飛ばし」と呼ばれる現象が話題になる一方で、実は関西でも前向きな動きが進んでいます。
それが、新たなアリーナ施設の建設計画です。
まず注目したいのが、兵庫・神戸に誕生予定の「ジーライオンアリーナ神戸」。2025年開業予定で、約1万人を収容できる規模になる見込みです。
ライブやスポーツ、地域イベントにも対応可能な多目的アリーナとして、すでにファンや地元メディアの間でも話題になっています。
さらに、大阪市の森ノ宮地区でも新アリーナの計画が進行中。
こちらも約1万人規模で設計されており、関西におけるライブの“新しいハコ”の選択肢として期待されています。

新しいアリーナがあるだけで、アーティストの“来る理由”になるんです!
これで「関西飛ばし」にブレーキがかかる?
これらの新施設が完成すれば、今まで首都圏に集中していたアリーナツアーの流れにも変化が訪れる可能性があります。
特に演出や動線の自由度、機材設置のしやすさなど、アーティスト側のニーズを満たす設計がされていれば、関西がツアーの主要地として再び注目される未来も、決して夢ではありません。
現に、Kアリーナ横浜などの首都圏アリーナも、新設されたことで一気にライブ開催が増えた経緯があります。
同じように、神戸や大阪に新しい“ライブの聖地”が誕生すれば、ファンにとっても地元で楽しめる機会が格段に増えるでしょう。
ただし、建設されるだけで状況がすぐに劇的に変わるわけではありません。
新アリーナの完成と同時に、地元の熱量や行政・企業のサポート、そしてファンの声が重なってこそ、ようやく関西が“選ばれる地域”になっていくのです。
関西ファンにできることとは?
関西でのライブ開催をもっと増やすには、会場や運営側の努力だけでなく、私たちファンのアクションも大きな力になります。
実は、「この地域には熱心なファンが多い」「しっかり集客が見込める」と判断されればされるほど、関西がツアーに組み込まれる可能性は高まるのです。
① 関西公演のチケットを積極的に購入する
これは最もシンプルで、かつ最も効果的なアクションのひとつです。
「関西のチケットが完売した」という実績は、アーティストや運営サイドにとって大きな指標になります。
たとえ少人数のライブであっても、“しっかりと席が埋まる”という事実は、
「関西はやっぱり強い」と判断される材料になるのです。
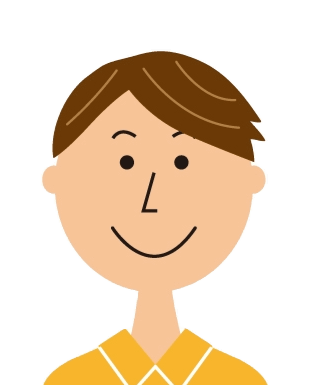
「行きたい」だけじゃなく「実際に行く!」ことが何よりのメッセージ!
② SNSでの応援・発信
今やSNSでの反応は、ツアー構成や開催地の決定にも影響を与えるほどの影響力を持っています。
「#関西公演待ってます」「#大阪にも来てほしい」といったハッシュタグ付きの投稿は、運営や事務所にファンの声を届けるための“見える可視化”となります。
投稿が多ければ多いほど、「こんなに関西にファンがいるんだ」と感じてもらえるチャンスにも。
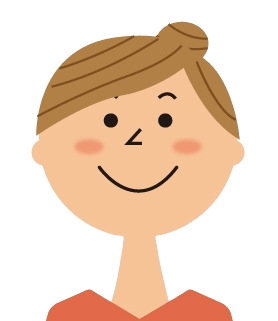
SNSの盛り上がりが、実際の開催地変更につながった例もあるんです!
③ 地元アーティストやイベントへの参加
ライブは大物アーティストだけのものではありません。
地元で活躍するアーティストのライブや、地域で開催される音楽イベントに足を運ぶことも、地元カルチャーの底上げに繋がります。
地域全体の音楽熱が高まることで、メディアや行政も注目しやすくなり、「音楽の街・関西」としてのブランド力を高めていくきっかけに。
④ 自治体やメディアへの提言や意見発信
意外と知られていませんが、ファンの声が行政の動きを後押しすることもあります。
例えば「地域にライブ向けの施設を作ってほしい」「助成金を活用してイベントを誘致してほしい」といった要望を、SNSや市民アンケートなどを通じて発信することで、政策や予算の動きに影響を与える可能性も。
地域メディアやFM局などにメッセージを送るのも効果的です。
“声を上げること”から、変化は始まります。
関西でライブをもっと楽しめるようになる未来は、遠い話ではありません。
ファン一人ひとりの行動や声が、地域に新しい風を吹かせていくのです。
まとめ:ライブの未来は“関西の声”で変えられる
2024年現在、音楽ライブやコンサートの現場では、アリーナクラスの大規模公演が主流になりつつあるという大きな潮流が生まれています。
そのなかで、どうしても会場数やインフラが整った首都圏にライブが集中する傾向が強くなっているのは事実です。
とはいえ、関西がこのまま“飛ばされる”存在であり続けるとは限りません。
むしろ今は、**ジーライオンアリーナ神戸や森ノ宮アリーナといった新施設の登場が期待される“転機”**にあります。
このチャンスを実りあるものに変えていくには、ファン一人ひとりの小さな行動が欠かせません。
チケットを買うこと、SNSで声を上げること、地元イベントに参加すること――そのすべてが、未来のライブカルチャーを支える大切な力になるのです。
「関西はライブが少ないから仕方ない」と諦めるのではなく、
「だからこそ、関西にも来てもらえるように応援しよう」と考えるファンが増えれば、
関西が再び“ライブの街”として盛り上がる日は、きっと遠くありません。
関西の音楽文化を守り、育てていく未来は、私たち自身の手の中にあります。
小さなアクションから、ぜひあなたも参加してみてくださいね。

今日の“応援”が、明日のライブを呼び寄せるかもしれません!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が少しでも、あなたの音楽体験を豊かにするヒントになれば幸いです。