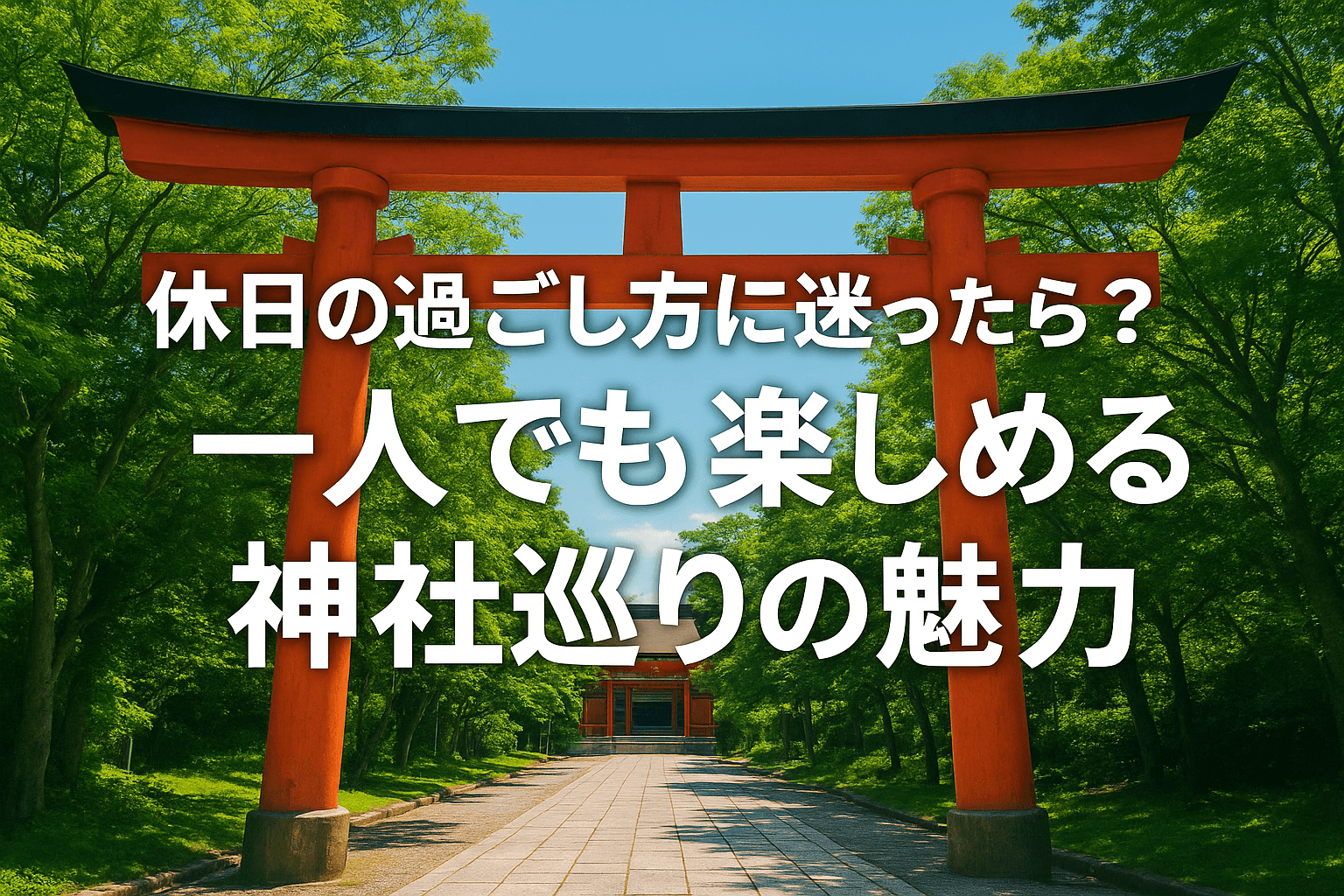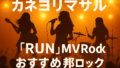はじめに:予定がない休日こそ「神社巡り」へ
天気が良くてお出かけ日和なのに、特に予定がない…。
そんな日はありませんか?家にいるのも悪くないけれど、せっかくの休日、外に出ないのはもったいない気がする。
そんな時におすすめしたいのが 「神社巡り」 です。
一人で気軽に楽しめて、歩くだけでちょっとした旅気分も味わえる。
しかも、御朱印を集めながら巡ると達成感もあり、心も体もリフレッシュできる休日になります。
神社巡りの魅力とは?
1. 健康的な散歩になる
神社は駅から少し離れていることが多く、1日で2〜3か所巡るだけでも自然と歩数が稼げます。
ただの散歩と違って「目的地=神社」があるので、歩くのが楽しく感じられるのもポイント。
住宅街を通り抜けながら「こんな素敵な家があるんだ」と街並みを楽しめるのも醍醐味です。

目的を持った散歩は疲れを感じにくいので、運動が苦手な人にもおすすめ!
2. 集める楽しさ=御朱印の魅力
御朱印巡りの魅力は「集める楽しさ」。
御朱印帳に少しずつ増えていく墨文字や朱印は、ポケモンGOのような“収集感覚”で楽しめます。
最近ではカラフルなデザインや季節限定の御朱印もあり、同じ神社でも訪れるたびに違った楽しみが待っています。
「御朱印はアート作品のように美しいものも多く、眺めるだけで気分が上がります!」
3. 心が整う癒しの時間
街中の喧騒から一歩入った神社の境内。そこには、凛とした空気と静けさが広がっています。
信仰心が強くなくても、不思議と気持ちが落ち着くのが神社の魅力。
「なんとなく気分がモヤモヤしている」
そんな時こそ、神社の静寂に身を置くことで、自然と心が整っていきます。
4. 一人だからこそ楽しめる自由な旅
御朱印巡りは一人で楽しむからこそ自由度が高い趣味です。
誰かと一緒だと歩き回るのが大変に感じるかもしれませんが、一人なら気ままに寄り道もできます。
買い物や外出のついでに「この近くに神社ないかな?」と調べて立ち寄るのもおすすめ。
予定+αで充実した時間が作れます。

御朱印巡りは観光ではなく“参拝”が目的。神様への礼儀を忘れずに!
5. 新しい街との出会い
神社巡りをしていると、普段降りない駅や知らない街に行く機会が増えます。
「今日はこの沿線の神社を攻めてみよう」と計画して出かけるのも楽しいですし、帰りに見つけた居酒屋やカフェでひと休みするのもまた特別な時間になります。
御朱印巡りをもっと楽しむポイント
1.御朱印帳の選び方
御朱印巡りを始めるなら、まずは「御朱印帳」を用意しましょう。
一昔前までは神社やお寺でしか手に入らなかった御朱印帳ですが、今ではネット通販や雑貨店でも種類豊富に販売されています。
和柄の伝統的なものから、モダンでおしゃれなデザイン、動物や花のイラスト入りなど、見ているだけでも楽しくなるほどのラインナップです。
御朱印帳は、ただ御朱印を集めるためのノートではなく「旅の記録帳」としての役割もあります。
表紙のデザインを見ただけで、「あの時、あの神社を訪れたな」と思い出がよみがえることも。
だからこそ、自分の気分が上がる一冊を選ぶことが大切です。
また、神社ごとにオリジナル御朱印帳を頒布していることもあります。
限定デザインや地域ならではのモチーフが描かれているので、旅先で見つけたらチェックしてみると、より特別感のある御朱印巡りが楽しめます。
2.季節限定の御朱印を探そう
御朱印には、実は「季節限定」や「行事限定」のものが存在します。
春は桜や菜の花、夏は花火や七夕、秋は紅葉、冬は雪景色や干支など、その時期ならではのモチーフがデザインされた御朱印をいただける神社が増えてきました。
同じ神社でも、季節や行事に合わせて御朱印が変わるので、リピーターが多いのも納得です。
実際に「春と秋、両方訪れて御朱印を見比べて楽しむ」という参拝者も少なくありません。

SNSで“限定御朱印”を検索すると、最新の情報が出てきます!
また、御朱印は「一期一会」の出会いでもあります。
その時しか手に入らない御朱印を求めて、遠方から参拝に訪れる人も多く、御朱印巡り自体がひとつのイベントになっているのです。
神社参拝の基本マナー
1.参拝の流れ
神社に訪れたら、まず大切なのは「正しい順序で心を整えて参拝すること」です。
せっかくの御朱印巡りも、参拝の作法を知っておくことでより充実した時間になります。
- 鳥居をくぐる前に一礼
鳥居は「神様の領域」と人の世界を分ける境界線。
くぐる前に軽く一礼をすることで、「これからお邪魔します」という気持ちを神様に伝えられます。 - 手水舎で手と口を清める
参道を進むと、多くの神社には「手水舎(ちょうずや)」があります。
柄杓を使って左手、右手、口の順に清めるのが基本。
これには「心身を清らかにしてから神様に会う」という意味が込められています。 - 本殿で参拝(二礼二拍手一礼)
本殿では「二礼二拍手一礼」が基本作法。
深いお辞儀を2回、手を合わせて2回拍手、最後にもう一度お辞儀をします。
この動作には「敬意を表す」「感謝を伝える」という意味があります。 - 御朱印をいただく
参拝を終えてから御朱印をいただくのが正しい順序。
神様にご挨拶を済ませてから記録をいただく、という流れを大切にすると、御朱印帳の一枚一枚にも自然とありがたみが増していきます。
2.お賽銭の縁起と意味
お賽銭には、実はちょっとした「語呂合わせの縁起」があるのをご存知でしょうか?
金額によって意味が込められており、昔から多くの参拝者に親しまれています。
- 5円:「ご縁がありますように」
- 15円:「十分なご縁」
- 25円:「二重のご縁」
- 41円:「始終良い縁」
- 50円:「見通しが良い未来」
このように、ただの金額ではなく「縁起を担ぐ」という楽しみ方もあります。

金額の多さよりも、“感謝の気持ち”を込めることが一番大切!
実際、お賽銭の本来の意味は「神様への感謝を形にしたもの」。
そのため、必ずしも縁起の金額でなくても大丈夫です。
日頃の感謝やお願いごとを心に込めてお賽銭を入れることが、何よりも大切なマナーなのです。
神社巡りの始め方:初心者向けステップ
神社巡りは特別な準備や知識がなくても始められるのが魅力です。
ここでは初心者の方でも気軽に楽しめるステップをご紹介します。
- まずは近所の神社を検索してみる
大きな有名神社に行かなくても大丈夫。
意外と知られていないのが、地域の小さな神社でも立派な御朱印をいただけることです。
Googleマップや「神社+御朱印」で検索すると、意外な発見があるかもしれません。 - 御朱印帳を用意する(ネットでもOK)
御朱印帳は神社やお寺で直接購入するのも良いですが、最近はネットや雑貨店でもおしゃれなものが豊富。
自分好みのデザインを選ぶと、神社巡りのモチベーションがぐっと高まります。 - 週末に1〜2か所からスタート
最初からたくさん巡る必要はありません。
まずは「今日はこの神社だけ」と気軽に訪れてみましょう。
ひとつひとつ丁寧に参拝しながら御朱印をいただく方が、思い出にも残りやすいです。 - 慣れてきたら沿線をテーマにして巡る
少し慣れてきたら、電車やバスの沿線をテーマにして1日で複数の神社を訪ねるのもおすすめ。
旅気分も味わえて、街歩きや食べ歩きと組み合わせれば「小さな旅行」に早変わりします。 - SNSや地図アプリで限定御朱印をチェック
季節限定や行事限定の御朱印は、公式SNSや参拝者の投稿で情報が見つかります。
「こんな御朱印があるなら行ってみよう」と旅の目的ができるのも魅力です。

無理せず“今日は1社だけ”と決めても十分に楽しめます
実際、御朱印巡りを長く続けている人の多くは、マイペースを大切にしています。
自分のペースでコツコツ巡るからこそ、習慣として長く続けられるのです。
さらに、ちょっと知識をプラスすると参拝がもっと面白くなります。
たとえば『古事記』や『日本書紀』に登場する神様がどんな神様なのかを知っておくと、「あ、この神社にはこの神様が祀られているんだ」と理解が深まり、参拝の楽しさが倍増します。
難しく感じるかもしれませんが、最近はYouTubeなどで分かりやすく解説してくれている動画もあるので、気軽にチェックしてみるのもおすすめです。
まとめ:心も体も満たされる「ひとり神社時間」
予定がなくても、神社巡りは「散歩」「収集」「癒し」を一度に味わえる、とても贅沢な休日の過ごし方です。
境内を歩くことで自然と体が整い、御朱印帳に一つずつ増えていく達成感はちょっとした宝物のように感じる事でしょう。
さらに、新しい街との出会いや、静かな神域で得られる心の落ち着きは、日常のリセットにぴったりです。
最近は、御朱印や参拝の作法を丁寧に教えてくれる神社も多く、初心者でも安心して楽しめる環境が整っています。
また、SNSを通じて季節限定の御朱印情報を知る人が増えたことで、神社巡りは「趣味」としても広がりつつあります。
誰かと一緒でなくても大丈夫。
むしろ一人だからこそ、自分のペースで自由に歩き、気の向くままに神社をめぐれるのが最大の魅力です。
次のお休みはぜひ、あなたも「ひとり神社時間」を楽しんでみてください。
きっと心も体も軽くなり、また新しい日常を頑張れるエネルギーをもらえるはずです。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。