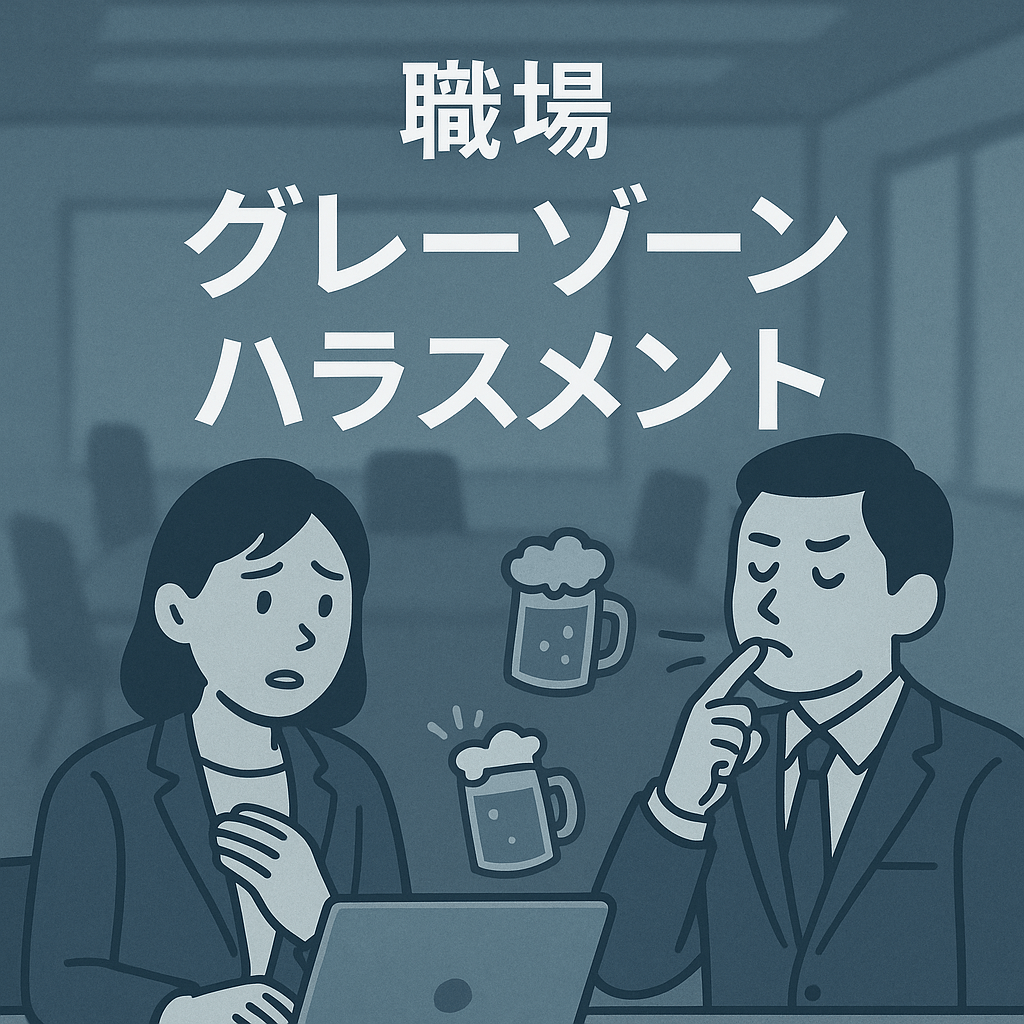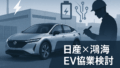「え、それってハラスメント?」気づきにくい“グレーゾーン”の怖さ
「俺の若い頃はさ」「今時の若者は……」
そんな上司の小言や、「あなたのためを思って」と一方通行なアドバイス。
はたから聞けば「ただのコミュニケーション」で済むようにも思えます。でも、受け手にしてみればモヤモヤが募る…。
近年、職場で問題視されているのが「グレーゾーンハラスメント」です。
これは、パワハラやセクハラとまでは断言しにくいけれど、相手に不快感やプレッシャーを与える言動のこと。企業のコンプライアンスや人間関係をむしばむ“静かな毒”のような存在です。

小さな不快感の積み重ねが退職理由にもつながるんです。
グレーゾーンハラスメントは、法律で明確に禁止されるラインを越えないため、発言した本人も「良かれと思ってやった」と自覚が薄いことが多いのが厄介なポイント。
そんなグレーゾーンハラスメントの実態を、実際の調査データをもとに解説し、企業や働く人ができる対策を具体的にまとめました。
グレーゾーンハラスメントの定義と特徴
ハラスメントの「白黒つけにくい」境界線
グレーゾーンハラスメントとは、法的に「パワハラ」「セクハラ」とは断定しづらいが、受け手が心理的なストレスを感じる言動のことです。
具体例はこんなものがあります。
- ため息や舌打ちなどの不機嫌な態度
- 社内飲み会・接待への参加強制
- 個人的な価値観を押し付ける説教
- プライベートな質問をしつこくする

「このくらい普通じゃない?」

本人がそう思っていても、相手は強いストレスを感じているかも。
言われた側は「ハラスメントだ!」とまでは訴えにくい。
でも確実に「嫌だな」「もう辞めたい」と感じる人も多いのが現実です。
グレーゾーンを放置するリスク
- 職場の雰囲気が悪化
- 社員のモチベーション低下
- 優秀な人材の流出
- ハラスメント訴訟リスクの拡大
実際、「法的なパワハラじゃないから大丈夫」と放置すると、チームの空気はどんより。
表立った衝突はなくても、じわじわと組織を侵食していきます。
最新調査で見えた「不快な言動」の実態
東京都内の企業が実施した2025年の調査結果からは、グレーゾーンハラスメントがいかに身近にあるかがわかります。
5割が「不快な言動を受けた経験あり」
全国のビジネスパーソン1196人を対象にしたインターネット調査では、約5割が「職場で不快な言動を受けた経験がある」と回答しています。
主な内容を見てみましょう。
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| ため息や舌打ち、あいさつを返さないなど不機嫌な態度 | 26.2% |
| 飲み会や接待への参加強制 | 16.2% |
| 過去の慣習・価値観の押し付け | 14.5% |
| プライベートな質問の強要 | 12.0% |
「退職を検討した」人は45.8%
さらに「そうした言動を受けて退職を検討したか」という問いには、45.8%が「はい」と回答。
特に「無視・仲間外れ」や「飲み会参加強制」は、7割近くが退職を考えるほどの強いストレス要因でした。
「誰が見てもパワハラやセクハラに該当するのであれば、企業として対応すべきことは法律上明らか。しかし、グレーゾーン事案は対応が難しく、それゆえに注意が必要だ」
ー成蹊大学 原昌登教授(労働法)
「これはハラスメントじゃない」と思い込むのではなく、受け手の感じ方を尊重する意識が大切です。
加害意識が薄い「良かれと思って」の落とし穴
調査では「自分はグレーゾーンハラスメントをしたことがない」と答えた人は約6割でした。
しかし実際には、
- 交際相手の有無などプライベートを聞いたことがある:15.3%
- 不機嫌な態度をとったことがある:11.4%
こうした「本人は気づかないうちにやっている」ケースが多いのです。

相手がどう感じるかを意識することが大切。
また、グレーゾーン的な言動をした人の約6割が「良かれと思ってやった」と認識していたことも判明しています。
- 世代間ギャップ
- 社風や古い慣習
- 個人の価値観の押し付け
こうした背景も、「自分は悪くない」という無自覚を生む要因です。
「飲み会強制」問題の深刻さ
「お付き合い」文化とハラスメントの境界
「断ったら空気が悪くなるから…」
「行きたくないのに断れない」
社内の飲み会強制は、上司や先輩からすると「仲良くなるため」「コミュニケーション」といった善意の場合もあります。
でも、立場上断りにくい部下にとっては強いプレッシャーに。

「強制じゃないよ、って言われても断れない空気がしんどいんだよね。」
特に若い世代ほど「プライベートを大事にしたい」という意識が強く、価値観のギャップが摩擦を生みます。
調査データで見る「飲み会ハラスメント」
- 飲み会・接待強制を受けた人の16.2%が「不快な言動を経験」
- そのうち約7割が退職を検討
飲み会の誘い方や頻度、断ったときの反応など、細かいところに「強制性」がにじむケースも多いのです。
企業に求められる「グレーゾーン対策」
社内規定の整備状況
同調査では、グレーゾーンハラスメントを抑制する社内規定が整っていない企業が特に中小企業で多いことも明らかになっています。
- 社内ガイドラインが不十分
- 管理職研修が形だけ
- 相談窓口が機能していない
これでは「グレーゾーン」を放置しやすくなってしまいます。
有効な取り組み例
- 「不快な言動リスト」を社内で共有
- 世代間ギャップを埋めるコミュニケーション研修
- 部下への指導時に「一方通行」にならない工夫
- 匿名で相談できる外部窓口の設置
原教授は「立場を利用した言動により心理的負担を生じさせることを禁止するなど、分かりやすい規定を整備する」ことを提案しています。
働く個人ができる「グレーゾーン」対策
【H3】受け手側のセルフケア
- 「これが嫌だった」と自分の気持ちを自覚する
- 信頼できる同僚や友人に相談
- 無理に笑顔で受け流さない

そんな風に思わなくてOK。不快なものは不快です。

そんな風に思わなくてOK。不快なものは不快です。
伝え方の工夫
- 「私には少しきつく感じます」と主語を自分にして伝える
- 断りづらい誘いには「スケジュールが合わない」と具体的に
- 直属の上司以外の相談ルートを確認
管理職や周囲ができること
- 相手の立場で「これ言われたらどう感じるか」を想像
- 注意や指導の際は目的と期待を共有
- 部下の反応を観察し、表情や態度の変化を見逃さない

「結局コミュニケーションが大事なんだね。」
まとめ:グレーゾーンを減らすことは、みんなのためになる
グレーゾーンハラスメントは、明確な「NG」ではないからこそ、見逃されがちです。
しかしその言動は、知らず知らずのうちに受け手の心にストレスを与え、モチベーションや自信を少しずつ奪っていきます。
「そんなつもりはなかった」という言葉では済まされないこともありますし、
「嫌だったけど言い出せなかった」という沈黙は、職場の空気を少しずつ重くしてしまいます。
こうした小さなすれ違いを減らすことは、単に“誰かのため”ではなく、
チーム全体の信頼関係を深め、働きやすさや仕事の効率を高めることにつながります。
結果的に、企業の魅力や生産性の向上にも寄与する大切な取り組みです。
お互いが少しずつ気づき合い、歩み寄ることで、もっと安心して働ける環境はつくれるはずです。
この記事が、そんな一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。