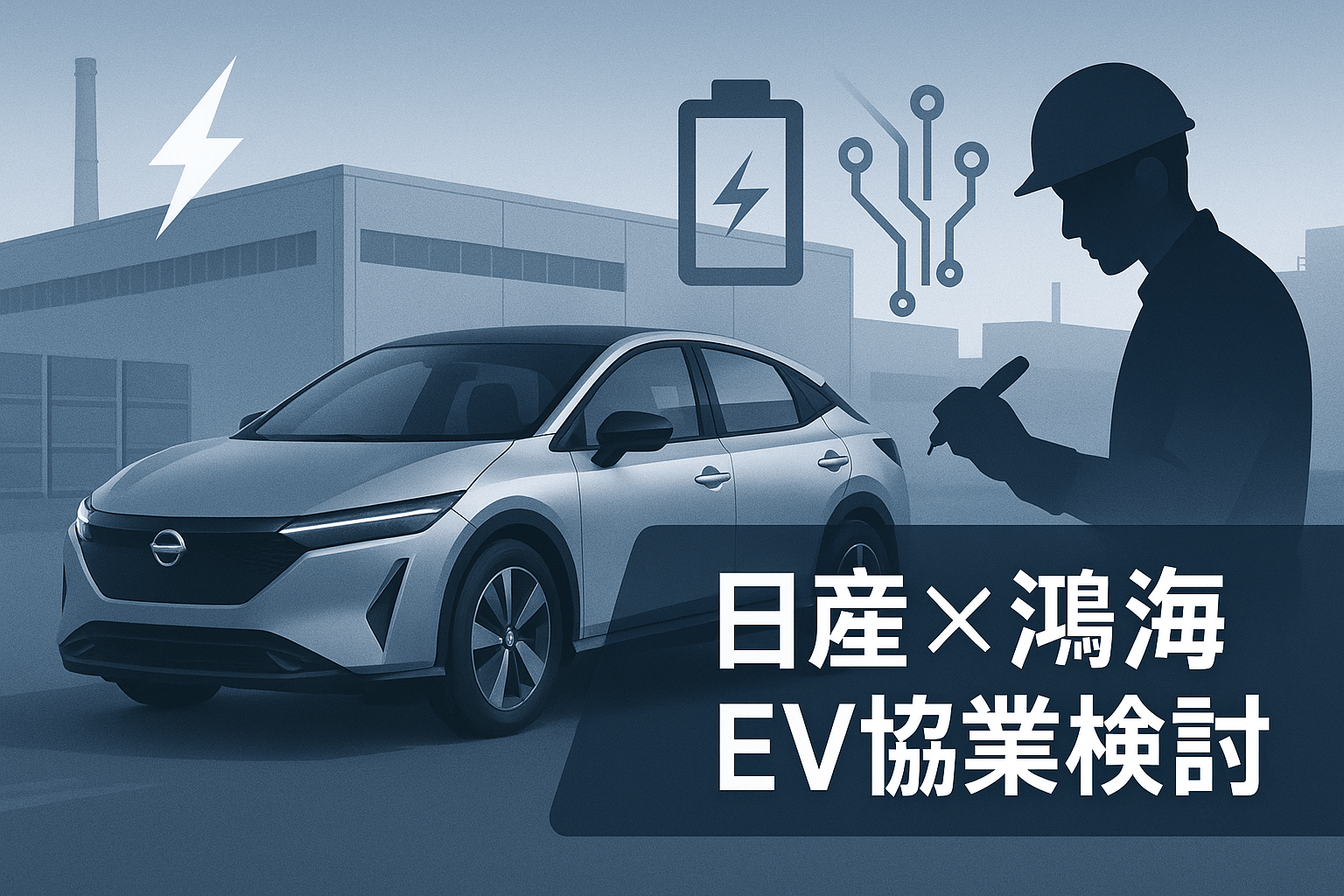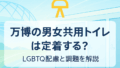日産再建の切り札となるか?鴻海とのEV協業構想が報じられる
経営再建の渦中にある日産自動車が、新たな一手として注目されているのが台湾の電子機器大手・鴻海(ホンハイ)精密工業との電気自動車(EV)をめぐる協業案です。
2025年7月上旬の報道によれば、閉鎖検討中だった神奈川県横須賀市の追浜(おっぱま)工場で、鴻海が設計したEVを受託生産する計画が浮上しているとのこと。
もしこの構想が実現すれば、日産のEV戦略を大きく進展させる可能性があるだけでなく、地元の雇用維持や地域経済へのプラス効果も期待されます。
一方で、自動車メーカーとしてのブランド戦略や技術流出への懸念、国内製造業の在り方そのものを問う論点も浮かび上がります。
この記事では、日産と鴻海のEV協業案について、背景や影響、今後の見通しまでを分かりやすく解説していきます。
日産と鴻海のEV協業検討報道の概要
2025年7月、複数の報道によって明らかになった今回の協業案。
以下のような点がポイントとなっています。
- 日産が追浜工場で鴻海設計のEVを受託生産する案
- 工場閉鎖を回避し、地域雇用を維持する可能性
- 日産のEV戦略強化に向けた新たなパートナーシップの模索
鴻海(ホンハイ)といえば、Apple製品などの製造を請け負う世界的な電子機器メーカーであり、EV事業への本格参入も進めています。

「受託生産って何?」

他社の製品を代わりに作る仕事のこと。
鴻海はその実績が世界トップクラスです。
日産はここ数年、アライアンスの再編や国内工場の生産最適化などの課題を抱えており、追浜工場も閉鎖候補として取り沙汰されていました。
今回の構想は、そうした状況に一石を投じる提案となっています。
追浜工場とは?閉鎖案から協業生産案へ
神奈川県横須賀市にある追浜(おっぱま)工場は、日産にとって歴史ある基幹工場のひとつです。
- 稼働開始:1961年
- 主力生産車種:ノートなど
- 従業員数:約1000人規模
国内需要の減少とグローバル生産体制の再編により、数年来、生産調整の対象となっていました。
工場閉鎖は地域雇用に直結するため、労働組合や自治体からも強い反発の声が上がっていました。
今回のEV協業案が実現すれば、追浜工場の存続に新たな道が開かれる可能性があります。
鴻海(ホンハイ)精密工業とはどんな企業か
鴻海精密工業(Foxconn)は、世界最大級の電子機器受託生産企業です。
- 本社:台湾・新北市
- 主な取引先:Apple、ソニー、Microsoftなど
- 従業員数:数十万人規模
- 年商:約20兆円以上
もともとはスマートフォンやパソコンの製造で知られていましたが、近年はEV事業を新たな柱に据えています。
- EVプラットフォーム「MIH」の提供
- 他社ブランド向けEVの設計・受託生産
- EVバッテリーの開発

「鴻海(ホンハイ)って車の会社じゃないよね?」

もともとは電子機器の下請けだったみたい。
でも今はEVにも本格参入しているんです。
日産と手を組むことで、日本市場へのEV展開を一気に進める狙いがあると考えられます。
EV業界の現状と背景
EV業界では、ここ数年で構造的な変化が加速しています。日産が鴻海(ホンハイ)との協業を模索する背景にも、この動きが大きく関係しています。
EV生産コストの課題
- バッテリーの価格が高止まり
- 投資回収に時間がかかる
- 新興勢力との価格競争が激化
受託生産モデルの拡大
- EVプラットフォームを外部提供する動き
- 自動車メーカーは開発負担を減らし、ブランド展開に集中
- 鴻海はまさにこのモデルの代表格です
このように、EV時代の競争は”全部自社で作る”という従来のモデルから変わりつつあるのです。
協業によるメリット:雇用維持・コスト削減
雇用維持
追浜工場でのEV生産が実現すれば、1000人規模の雇用が守られる可能性があります。
これは企業の社会的責任としても大きな意味を持ちます。
生産コストの削減
鴻海の大量生産ノウハウを活用することで、日産は生産効率を高められる可能性があります。
- グローバルなサプライチェーンの活用
- 設計の標準化
- ボリュームによるコストダウン
こうした協業モデルは、資源が限られる中での戦略的選択肢になりえます。
考えられる課題と懸考えられる課題と懸念
もちろん、どんな協業にもリスクはつきものです。
今回の日産と鴻海(ホンハイ)の構想にも、いくつか気になるポイントがあります。
ブランド価値の維持
日産といえば長年築いてきた「技術の日産」というブランドイメージがあります。
受託生産という新しい形で車を提供する場合、それが本当に“日産らしい”と消費者に感じてもらえるかどうかは重要な課題です。
- 鴻海(ホンハイ)設計のEVを「日産車」として販売する可能性
- デザインや性能で日産らしさをどこまで保てるか

「鴻海が作った車を日産が売るの?」

受託生産モデルだとそうなる可能性もあります。
ただし、ブランドの一貫性をどう保つかが問われます。
技術情報の流出リスク
EVの設計や製造には、これまで培ってきた高度な技術が詰まっています。
鴻海(ホンハイ)と協力する以上、ある程度の技術共有は避けられません。
その中で、技術的な優位性をどう守るかが大きな課題になります。
- 設計ノウハウが外部に漏れるリスク
- 鴻海がその技術を使って別ブランドのEVを開発・展開する可能性
地域コミュニティとの調整
今回の協業案では、追浜工場での雇用維持が注目されていますが、雇用形態や待遇の変化が生じる可能性もあります。
- 業務内容の変更や再教育の必要性
- 労働組合との合意形成
- 地元自治体との綿密な連携
短期的には工場閉鎖を回避できたとしても、将来にわたって安定的に雇用が続くかどうかはまだ見通せません。
長期的な視点での戦略と、地域に根ざした丁寧な説明・対応が求められるでしょう。
こうした複数の課題にどう向き合い、乗り越えていけるかが、今回の協業の成功を左右するカギになるといえます。
まとめ:日産再建のカギを握るEV戦略
今回の報道によって明らかになった日産×鴻海(ホンハイ)のEV協業構想は、単なる企業間の提携という枠を超え、国内製造業や地域社会、そして日本のEV戦略全体に大きなインパクトを与える可能性があります。
追浜工場を活用できれば、地域の雇用が守られるだけでなく、日産にとっても生産能力や開発資源を最適化する大きなチャンスになります。
加えて、鴻海(ホンハイ)が持つグローバルなサプライチェーンや量産ノウハウは、EV生産コストの削減にもつながると見られています。
一方で、受託生産によるブランド戦略の難しさや、技術情報の扱いといった課題も残されています。
協業が実現したとしても、そこから先の運用や関係構築がスムーズに進むかどうかは、今後の交渉と実行次第といえるでしょう。

雇用維持への期待はあるけれど、今後の交渉と具体化がカギになります。
日産の再建、そしてEV時代における日本のものづくりの行方を左右するこの協業案。
今後の動向に注目しながら、続報を待ちたいところです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。