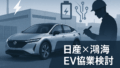2025大阪・関西万博の新しい試みとは?
2025年、大阪の夢洲(ゆめしま)で開催される「大阪・関西万博」。
「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、世界中から多くの人々が集まるこの国際的なイベントでは、これからの社会のあり方を問い直すような、さまざまな新しい取り組みが導入されます。
中でも今、注目を集めているのが「オールジェンダートイレ(男女共用トイレ)」の導入です。
性別を問わず誰でも利用できるトイレの設置は、日本の大規模な公共イベントでは非常に珍しく、これまでになかった試みとも言えます。
この新たな試みには、「多様性への配慮」や「すべての人が快適に過ごせる空間づくり」など、未来志向のコンセプトが込められています。
一方で、日本の文化や慣習に根差した“トイレに対する価値観”とのギャップから、「本当に定着するの?」「使うのに抵抗がある」という声があるのも事実です。
性の多様性が当たり前になりつつある現代において、公共トイレのあり方も変化が求められています。
大阪・関西万博は、その変化の“第一歩”として、社会全体に問いかけをしているのかもしれません。
この記事では、万博における男女共用トイレの具体的な設計や背景、LGBTQへの配慮のポイント、そして今後の課題まで、解説していきます。
万博で導入されるオールジェンダートイレとは?
未来の公共トイレ、その第一歩
2025年の大阪・関西万博では、「多様性」や「誰もが快適に過ごせる空間づくり」がコンセプトのひとつとなっています。
そんな中、大きな注目を集めているのが「オールジェンダートイレ(男女共用トイレ)」の導入です。
これまで日本では、公共トイレといえば“男性用”と“女性用”が明確に分かれているのが当たり前でしたよね。
でも今回の万博では、その常識を大きく変えるような、新しい形のトイレが会場に設けられます。
なんと、会場に設置されるすべてのトイレ個室のうち、およそ1割が性別に関係なく誰でも使える「個室型のオールジェンダートイレ」になるのです。
設計のポイントは「安心」と「使いやすさ」
その設計には、さまざまな工夫が詰まっています。
- 一方通行の通路を挟み、左右に30室以上の個室を配置
- すべての個室にサニタリーボックスを完備
- 通路の中央には、共用の手洗いスペースを設置
- 通路の奥には、男性用小便器も配置
このような構成にすることで、「性別を気にせず使える」だけでなく、「人の流れがスムーズで混雑しにくい」仕組みになっています。
とくに、女性トイレでよく見かける長い行列の解消にもつながるのではないかと期待されています。

誰でも使える安心な設計が、混雑緩和と多様性配慮の両立を目指しています!
実際に使われている様子は?
すでにメディアや事前公開で取り上げられた場面では、さまざまな人たちがオールジェンダートイレを利用している様子が見られました。
例えば──
- 鏡の前で化粧直しをする女性
- その隣で手を洗うビジネスマン風の男性
- ベビーカーを押した親子連れが通路を通る姿
こうした風景は、一見するとなんてことのない日常のように見えるかもしれません。
でも、これが“性別で空間が分かれていない”トイレであることを考えると、日本における新しい公共空間の在り方を象徴するワンシーンだと言えます。
一方通行の通路設計によって、すれ違いによるストレスを減らし、スムーズな導線が保たれているのもポイント。
衛生面でも安心できるよう、清掃体制の強化が想定されているのも嬉しいところです。

一方通行の設計は、プライバシー保護にも役立っているらしいです。
多様性に配慮したトイレ設計の意義とは?
性的少数者(LGBTQ)への配慮
これまでのトイレは「男性用」「女性用」と明確に分かれており、性自認と一致しない利用者にとっては精神的ハードルが高いものでした。
- トランスジェンダーの方がどちらに入るかで迷う
- 他者の視線や不安を感じる
- 子どもの性自認に対応した柔軟な空間がない
オールジェンダートイレは、こうした不安を軽減し、誰もが安心して利用できる空間を提供します。
女性トイレの行列問題の緩和
イベントや商業施設で見かける「女性トイレの長蛇の列」。この課題にもオールジェンダートイレは一役買っています。
- 個室数を増やすことで滞在時間を平準化
- 男女を問わない利用が可能に
これにより、時間的ストレスや不公平感の解消にもつながると期待されれています。
利用者の声:受け入れの実態と課題
では、実際にオールジェンダートイレを使った人たちは、どう感じているのでしょうか?
前向きな意見としては…
- 「普通のトイレとあまり変わらないから、気にならなかった」
- 「男性と女性が混在していても、特に不便を感じなかった」
- 「子どもと一緒に入れるので助かる」
といった声があり、若い世代や家族連れからは好意的な反応が目立っています。
一方で、慎重な意見や不安も確かに存在します。
- 「知らない異性の後に入るのはちょっと抵抗がある」
- 「個室でも音が気になるし、落ち着かない」
- 「慣れるまでは少し緊張する」
このような反応を見ると、やはり“これまでの常識”からの変化に、戸惑いを感じる人が一定数いることも否定できません。

賛否があるのは当然。でも、それは社会が変わろうとしている証拠でもあります!
万博は“社会実験の場”でもある
公共空間における受け入れの「試金石」
2025年の大阪・関西万博で導入されるオールジェンダートイレは、単なる“便利な新しいトイレ”ではありません。
むしろこれは、これからの公共空間がどうあるべきかを社会全体に問いかける大きな実験とも言える存在です。
この試みには、「利用しやすさ」だけでなく、次のような目的が込められています。
- 実際の利用状況をもとにしたデータの収集
- ユーザーがどのように感じたかという満足度の評価
- 利用者の声を受け止めて進める設計や運用の改善
こうした過程を通じて、万博以降に建設・改修される商業施設、駅、空港、学校などでも、オールジェンダートイレの導入が検討されていく可能性があります。

万博でうまくいっても、他の場所では“そのまま”では通用しないかも。現場に合った設計が必要です!
日本のトイレ文化にある“変化の壁”
性別を分ける習慣は根強い
日本では長いあいだ、「男性用トイレ」「女性用トイレ」というように、性別で空間を分けることが当たり前の文化が築かれてきました。
- 防犯への配慮
- プライバシーの確保
- 利用者の安心感
- 社会的な慣習や価値観の影響
こうした要素が絡み合っているため、「性別にとらわれないトイレ」という発想自体に違和感を覚える人がいるのも自然なことです。

実は、欧米の一部都市では“完全個室の共用トイレ”が広がりつつあります!
「安心して使える」には設計の工夫がカギ
抵抗感をどう減らすか?
「誰でも使える」という理想を現実にするためには、設置すればそれでOKというわけにはいきません。
むしろ大切なのは、「安心して使ってもらえる空間」をどうつくるか。
たとえば──
- 音漏れや視線を防ぐような個室の構造
- 入り口と出口が明確に分かれた一方通行型の動線
- こまめな清掃と衛生管理の徹底
大阪・関西万博で採用されているトイレは、まさにこうしたポイントをしっかりとおさえた設計になっています。
これから求められる視点と工夫とは?
普及に向けた“次のステップ”
オールジェンダートイレを社会全体に広げていくには、技術や構造だけではなく、人々の意識や受け入れ態度も大切な要素です。
今後の導入を進める上では、こんなポイントが求められるでしょう。
- 高齢者や子ども連れなども含めた幅広い世代への説明と配慮
- 利用者の声をもとにしたフィードバックと改善の継続
- 「清潔」「安心」「安全」をキープする運用体制の充実
どんなに良い設備が整っていても、「ちょっと不安かも…」と思われてしまえば、使ってもらえません。
だからこそ、“使いやすさ+心理的な安心”の両立が、今後の最大の課題なのです。

利便性だけでなく、「ここなら大丈夫」と思える安心感づくりがポイントです!
このように、万博は“未来の社会”を先取りして体験する場。
オールジェンダートイレの取り組みも、そのひとつとして、私たちの暮らしの選択肢を少しずつ広げてくれています。
まとめ:未来のトイレ文化へ向けて
オールジェンダートイレの導入は、単なる施設の“新しさ”ではなく、私たちの社会がどんな価値観を持ち、誰にとっても居心地のよい空間をどう実現するかという問いへの、ひとつの答えでもあります。
LGBTQなど多様な性のあり方に対する配慮はもちろん、女性トイレの混雑解消、子連れや介助者への配慮といった、実生活に直結する課題への対応としても大きな意味を持っています。
そして2025年の大阪・関西万博は、そうした新しい取り組みを社会全体で体験し、検証し、対話していく“実験の場”として、非常に重要なステージです。
これまでの日本のトイレ文化は、「清潔さ」「安全性」「礼儀正しさ」が重視されてきました。
その土台を活かしながら、「誰もが安心して使える空間」をどう形にしていくかが、これからの公共空間づくりのテーマになっていくでしょう。
設計や運営の工夫を重ねながら、私たち一人ひとりが少しずつ新しい形に慣れ、柔軟に受け入れていくこと。その積み重ねが、次世代にとって当たり前のインクルーシブな社会につながっていくはずです。
この記事を通して、オールジェンダートイレについて少しでも理解が深まり、皆さんの身近な話題として考えるきっかけになれば嬉しいです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!